日本には約120万世帯以上のシングルマザーが存在し、これは30年前の約1.5倍に増加しています。しかし、その現実にもかかわらず、シングルマザーに対して「ろくなやつがいない」という偏見が根強く残っています。
シングルマザーの相対的貧困率は約5割にも達し、2世帯に1世帯が貧困状態にあるとも指摘されています。こうした厳しい状況下で懸命に子育てと仕事を両立しているシングルマザーたちに、なぜこのような偏見が向けられるのでしょうか。本記事では、その理由を詳しく解説します。
シングルマザーに「ろくなやついない」と偏見が持たれる理由
ここから、シングルマザーに対する「ろくなやつがいない」という偏見が生まれる主な理由を3つ説明します。
理由1:公的支援への誤解と妬みによる偏見
シングルマザーは自治体や国から児童扶養手当など様々な公的支援を受けられる制度があります。けれども、一部の人々は、「シングルマザーは税金で楽をしている」「支援金を自分の娯楽に使っている」といった誤解を抱き、妬ましく思う傾向があります。
とりわけ、生活保護を受給している母子家庭に対し、「働かずに毎日遊んで暮らしている」といった偏見が語られることもあります。
しかし、実態はそれとは大きく異なります。多くのシングルマザーは経済的に自立しようと努力しており、その就業率は81.8%にも達していて先進国でもトップクラスです。つまり、大半のシングルマザーは仕事をしながら子育てをしており、それでも収入が十分でないためにやむを得ず公的手当で不足分を補っているのが現状です。
事実、ひとり親世帯の半数以上が貧困ライン以下の生活水準にあり、非正規雇用の場合シングルマザーの平均年収は約133万円という低さです。このように公的支援は決して「楽をするための贅沢」ではなく、最低限の生活と子どもの養育を支えるためのセーフティネットです。支援制度への誤解や嫉妬から生まれる偏見は、シングルマザーたちの実際の努力や苦境を正当に評価していないと言えます。
理由2:伝統的な家族観に基づく道徳的非難
日本社会では依然として伝統的な結婚観や家族観が根強く、一人親家庭に対する否定的な価値観が残っています。そのため、「結婚生活を全うできないのは本人の人間性に問題がある」「離婚する人は身勝手だ」という偏見がしばしば語られます。
実際、シングルマザー本人も離婚を決意する際に「離婚=自分に欠陥がある人」というレッテルを恐れるケースが少なくありません。しかし、離婚やひとり親になる理由は家庭ごとに様々であり、必ずしも本人の性格や倫理観の問題とは限りません。
例えば、日本の司法統計によると、女性の離婚理由の上位には「精神的な虐待(モラハラ)」「生活費を渡さない(経済的DV)」「暴力を振るう(身体的DV)」「配偶者の不貞行為(浮気)」などが挙げられています。具体的には、離婚調停を申し立てた女性の26.1%が「精神的虐待」、18.5%が「身体的暴力」、12.9%が「配偶者の異性関係(不倫)」を理由に挙げており、生活費を渡さないといった経済的DVも約28.9%にのぼっています。
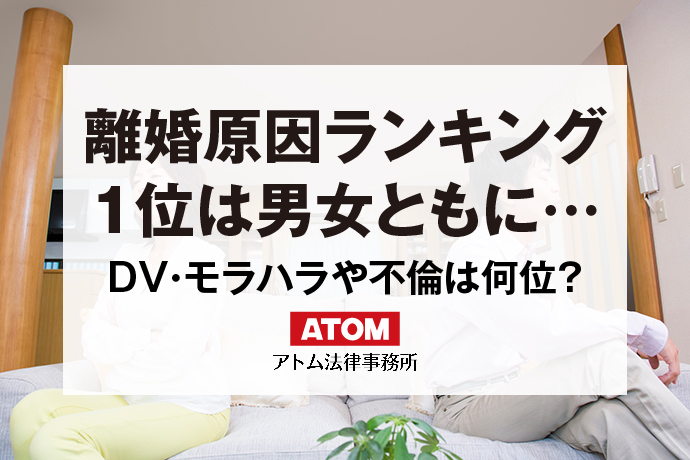
このように多くのシングルマザーは配偶者からの暴力や浮気など深刻な理由でやむなく離婚に至っており、決して「性格に問題があるから一人親になった」わけではありません。むしろDV被害から子どもと自分を守るために離婚という選択をしたケースも多く、それは責められるべきではなく勇気ある決断です。伝統的家族観に基づく一面的な非難や道徳的偏見は、シングルマザーの置かれた背景を無視した不当なものと言えるでしょう。
理由3:一部の事例とメディア報道による偏ったイメージ
偏見のもう一つの大きな原因は、メディアやインターネット上で拡散される偏ったイメージです。ニュースでは児童虐待やネグレクトなど一部の悲惨な母子家庭の事例がセンセーショナルに報じられることがあり、これがシングルマザー全体のイメージを悪化させる一因となっています。
また、SNSや匿名の掲示板では「シングルマザーはクズ」「頭おかしい」といった極端な決めつけが散見され、実際に「シングルマザー ふざけんな」という検索キーワードが月に3,600回も検索されているとのデータもあります。
こうした特定のネガティブな投稿やキーワードが強調されることで、あたかもそれが世間一般の総意であるかのような誤解が生じかねません。しかし、それらは一部の過激な意見や特殊な事例に過ぎず、全てのシングルマザーに当てはまるものではありません。
シングルマザーと性格には因果関係はない
上述したように、シングルマザーになる理由は様々であり、本人の性格や資質といった内面的な要因と直接結びつける根拠はありません。離婚や非婚のひとり親家庭に対して「本人に人間的問題があるはずだ」と見る向きがありますが、それは偏見に過ぎません。
実際、専門家の調査でも「ひとり親家庭で育つ子どもが問題を起こしやすい」という俗説を裏付ける医学的・心理学的根拠はなく、問題が生じるかどうかは経済状況や親のストレスといった環境要因によるところが大きいと指摘されています。

たとえば「ひとり親家庭の子はグレる(非行に走る)」という偏見がありますが、これは家族形態そのものより貧困や親の心理的疲弊が影響していると考えられており、家庭が一人親であること自体が子どもの発達に悪影響を及ぼすという科学的証拠はないのです。
言い換えれば、シングルマザーであることそれ自体がその人の性格的欠陥や子育て能力の欠如を意味するものでは全くありません。むしろ、多くのシングルマザーたちは困難を抱えながらも強い責任感で子どもを育てており、「1人で子どもを育て上げよう」「周囲に何も言われないよう立派に育てよう」という強い覚悟と努力を重ねているのです。
世間がシンママに厳しいのはなぜか?
ではなぜ、ここまで世間はシングルマザーに厳しい目を向けがちなのでしょうか。その背景には、日本社会特有の「自己責任論」や価値観が横たわっています。
離婚や未婚で母親になることに対し、「結局は本人の身から出た錆」「自分勝手に家庭を壊した結果だ」という無言の圧力が存在する、と指摘する声があります。
実際、1980年代には未婚の母に対して公的扶助を制限しようという政策動向もありました。例えば1984年には児童扶養手当法が「未婚の母には支給しない」よう改正されそうになった経緯があり、日本社会は長らく未婚・非婚の母親を公的支援の対象から排除してきた歴史があります。
こうした政策や社会通念が示すように、「シングルマザーになったのは自己都合なのだから、苦しくても自分で何とかすべきだ」という風潮が根強いのです。世間の風当たりが特に厳しいのは、離婚や未婚で母となった女性に対してであり、実際に過去には「未婚の母は身勝手だ」といった見方が多く聞かれました。
つまり「好きでシングルマザーになったのだろう」「甘えるな」といった偏った自己責任論が、支援や共感よりも先に立ってしまうのです。
さらに、日本では家族の問題はプライベートなものと捉えられやすく、ひとり親家庭の苦境が「外から見えにくい(顔が見えない)」まま放置されがちだという指摘もあります。その結果、問題の深刻さが社会に共有されず、シングルマザー自身も孤立しやすいという悪循環が続いてきました。世間の厳しさの裏には、こうした構造的な無関心や、伝統的家族観に反する存在への無理解があると考えられます。
まとめ:どこまで自己責任なのか?
シングルマザーに対する「ろくなやつがいない」という偏見を紐解いてみると、それは本人たちの実情とはかけ離れた一方的な見方であることが分かります。確かに結婚や出産にまつわる選択には個人の責任も伴いますが、その後の困難な生活は決して本人の努力不足や性格だけによるものではありません。
配偶者からの暴力や浮気で離婚を余儀なくされたケース、配偶者の死亡や失踪で突然シングルマザーになったケース、そして日本の社会制度や職場環境が十分でないために貧困に陥るケースなど、背景には本人の力だけではどうにもならない要因が多数存在しています。
例えば、離婚後の子どもの養育費について見ても、2016年時点でシングルマザーの56.0%が一度も養育費を受け取ったことがないと報告されています。わずか4人に1人程度(24.3%)しか継続して養育費を受け取れておらず、残りは父親からの経済的支援が途絶えたままです。
このように本来なら共同で負担すべき子育ての責任を一手に引き受けざるを得ないのが日本のシングルマザーの現状であり、これを単純に「自己責任」と片付けるのは酷と言えるでしょう。
大切なのは、シングルマザーたちが直面する課題を社会全体で正しく理解し、彼女たちを孤立させないことです。経済的困難や子育ての両立への支援策を拡充するとともに、偏見を改める意識改革も求められます。幸い近年では、シングルマザーの貧困や養育費不払いの問題が社会問題として認識され始め、行政も「こども家庭庁」の設置や養育費確保の取り組みなど一歩ずつ改善に動き出しています。
結論として、シングルマザーの置かれた状況は決して「どこまで自己責任か」と問えるような単純なものではありません。本人の努力だけで解決できない構造的な困難が存在する以上、必要なのは自己責任論ではなく、社会全体での支え合いと理解です。偏見のない目で一人ひとりのシングルマザーに向き合い、彼女たちの努力と経験に耳を傾けることが、偏見を解消し支援を行き渡らせる第一歩となるでしょう。

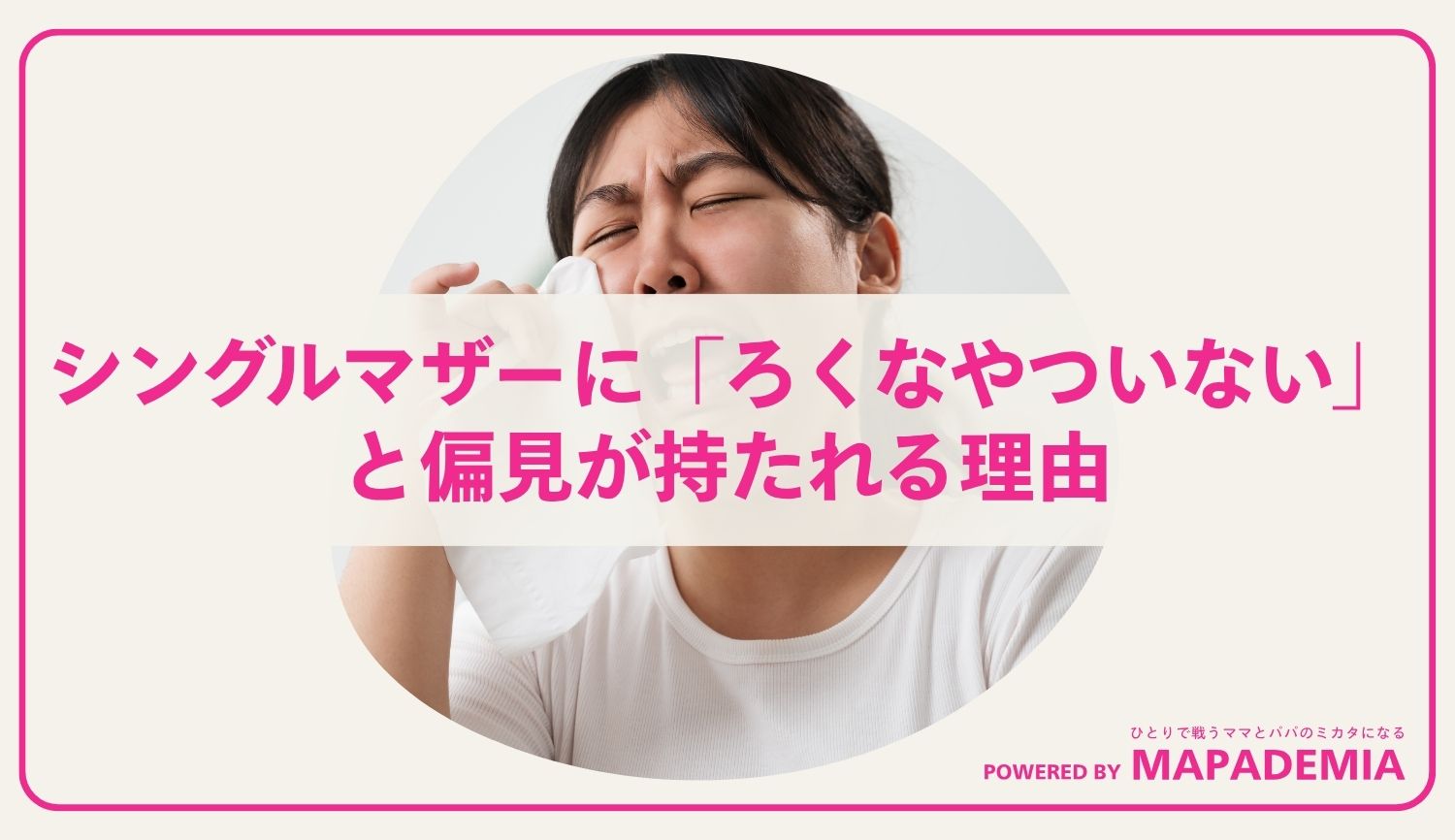









コメント