最近、「選択的シングルマザー」という生き方が注目を集めています。自らの意思で結婚せずに子どもを持つこの選択は、従来の家族観から外れるため、周囲から賛否両論があります。なかには、「頭おかしいのではないか」といった過激な批判もあります。
しかし、本当にこの価値観は非常識なのでしょうか?
本記事では、選択的シングルマザーとは何かを定義し、その選択が批判される理由を考察します。また、実際に後悔することはあるのか、そしてこの価値観の是非について多角的に検討します。従来の常識にとらわれず、家族のあり方について一緒に考えてみましょう。
選択的シングルマザーとは?
選択的シングルマザーとは、妊娠前から計画的にシングルマザーになることを選択して未婚で出産した女性のことです。簡単に言えば、「結婚はしないけれど自分の子どもが欲しい」と自ら望んで母親になる道を選んだ人を指します。
これは1980年代にアメリカの心理療法士ジェーン・マテスが提唱した概念で、彼女は「Single Mother by Choice(選択によるシングルマザー)」という組織も設立しました。日本でも近年、この言葉が紹介され始め、多様な家族の形の一つとして徐々に認知度が上がっています。
選択的シングルマザーは、日本ではまだ少数派ですが増加傾向にあります。厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果」によると、離婚や死別ではない未婚の母子世帯の割合は1993年には4.7%でしたが、2021年には10.8%に倍増しました。
未婚の母すべてが計画的に選んだとは限らないものの、この増加から自ら未婚で出産する女性が着実に増えていると推測できます。芸能人など著名人でも未婚で出産し母となる事例が報じられ、世間の関心も高まりつつあります。
もっとも、日本社会では結婚して子育てをする従来の家族観が根強く、未婚の母となる生き方はまだ珍しい存在です。そのため理解が追いつかず、選択的シングルマザーに対して否定的な声も少なくありません。「なぜわざわざ結婚せずに母親になるのか?」と疑問視されたり、心ない言葉を投げかけられることもあります。本当にそれほど非常識なことなのでしょうか。次章では、「選択的シングルマザーは頭おかしい」と批判される主な理由を3つに分けて解説します。
選択的シングルマザーは頭おかしいと批判されるのはなぜ?
選択的シングルマザーという選択肢に対し、否定的な人々が「信じられない」「非常識だ」と批判する背景には、いくつかの理由があります。これから代表的な3つの理由を順に説明します。
理由1: 子どもの福祉に対する懸念
一つ目の理由は、子どもの健全な成長への不安です。批判する人たちは「父親がいないなんて子どもがかわいそう」「そんな環境で子どもの心が大丈夫か?」と心配します。
確かに未婚の母の家庭では父親の存在が欠けるため、子どもは周囲の友達と自分の家庭環境が違うことに気づき、孤独感や寂しさを感じる可能性があります。また、社会的な偏見により学校や地域で「未婚の母の子ども」という理由でいじめや差別に遭う恐れも指摘されています。
さらに、「子どもには父親を知る権利があるのではないか」という倫理的な指摘もあります。国連の「子どもの権利条約」第7条では、「児童はできる限りその父母を知る権利を有する」とうたわれています。
しかし、日本には、例えば精子提供によって生まれた子どもが生物学上の父親を知る権利を保障する法律は整備されていません。そのため、意図的に父親不在の環境で子どもを産むことに対し、「子どもの出自を知る権利を奪うのでは」という批判があるのも事実です。
とはいえ、「母子家庭であること自体が子どもの心理的問題につながるという医学的証拠はない」とされています。イギリスの研究では、精子バンクによる出産で育つ母子家庭の子どもと、父母のいる家庭の子どもを比較して心理的適応に差はなかったとの報告もあります。
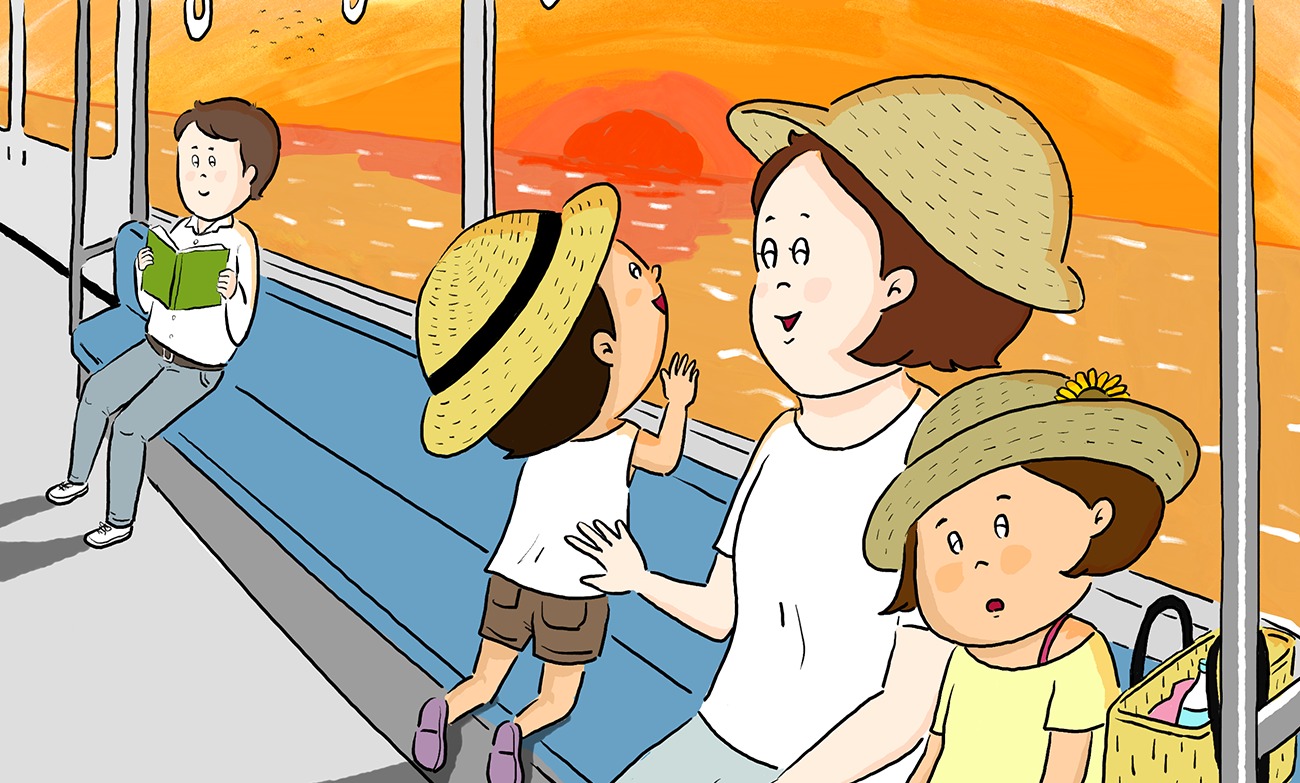
子どもの不安定さの原因は家庭形態そのものより、シングルマザー家庭が経済的困難に陥りやすく、母親がストレスを抱えがちな社会環境にあると分析されています。要は、十分な愛情と安定した生活環境があれば、片親でも子どもは健やかに育つということです。こうした知見から、「子どもがかわいそう」という批判は必ずしも根拠のあるものではなく、周囲のサポート次第で克服可能な課題だと言えるでしょう。
理由2: 経済的負担と育児の困難さ
二つ目の理由は、経済的・現実的な負担への懸念です。シングルマザーは一人で家計を支え、仕事と育児を両立しなくてはなりません。その大変さを思えば、「好き好んでそんな苦労を背負うなんて正気か?」という批判的な反応が出るのも理解できなくはありません。
現実問題として、日本のひとり親家庭は経済的に厳しいケースが多いです。実際、日本のひとり親世帯の貧困率は50.8%とOECD諸国でも最悪の水準であり、母子家庭の約45%が生活が「大変苦しい」と感じているという調査結果もあります。
平均して子ども一人を大学卒業まで育てるのに数千万円の費用がかかるとも言われるなかで、母親一人の収入だけですべて賄うのは容易ではありません。とりわけ非正規雇用だと収入が不安定になりがちで、病気やリストラで職を失えば途端に生活が行き詰まるリスクもあります。周囲に頼れる人がいなければ、母親が倒れた時に子どもを養う手段がなくなる不安もつきまといます。
また、育児と仕事の両立の難しさも見逃せません。配偶者がいない分、家事・育児から収入確保まで全責任を一人で背負うため、日々の負担は非常に大きくなります。子どもが小さいうちは保育園の送り迎えや急な病気対応、学校行事への出席などで仕事を調整する必要が生じます。
しかし、代わりに協力してくれる配偶者がいないため、その都度仕事か子どもかの苦渋の選択を迫られ、キャリアにも影響が出かねません。こうした現状から、「経済的にも時間的にも余裕がなく、子どもに十分なことをしてあげられないのでは?」という周囲の心配が、「無謀だ」「身の丈に合わない」という批判的な言葉につながっているのです。
理由3: 伝統的家族観に基づく偏見
三つ目の理由は、社会的・文化的な偏見や固定観念です。日本では長らく「家族とは結婚した男女とその子どもからなるもの」という伝統的家族観が根強く、未婚の母という存在自体に抵抗を感じる人もいます。「子どもは本来、父親と母親二人で育てるべき」「結婚せず子どもだけ持つなんて受け入れられない」といった意見は、その典型でしょう。
要するに、「自分の常識から外れた生き方=おかしい」という発想で批判しているわけです。
実際、ひとり親と未婚の子どものみの世帯は全体の約6.3%と少数派であり、目立つ存在であるがゆえに周囲の無理解にさらされやすいのも事実です。多様性を認めようという社会の流れがあるとはいえ、人々が自分と異なる価値観をすんなり受け入れるには時間がかかります。
結果として、未婚で出産する女性に対して心ない言葉を投げかけたり、「自分勝手だ」「常識はずれだ」とレッテル貼りをする人が出てきてしまうのです。
なかには、「未婚で子どもを産むなんて無責任だ!」といった批判もネット上で見受けられます。しかし、こうした声を上げる見ず知らずの他人たちは、その女性の子育てや人生に何の責任も負ってくれません。いわば完全な部外者であり、当事者ではないからこそ無責任に非難できている面もあるのです。
むしろ、結婚生活がうまくいかず離婚や家庭内暴力に苦しんでいる人に対しては「それでも子どものために我慢するのが普通」と言い、未婚で産めば「子どものためにならない」と言う――そんな風に他人の家庭を批判する人たちこそ、古い偏見に囚われていると言えるのかもしれません。
選択的シングルマザーになる条件
選択的シングルマザーという道を選ぶには、生半可な気持ちでは務まりません。経済面・精神面での十分な備えに加え、周囲の協力や将来への対策も必要です。ここでは、未婚で母になるために欠かせない3つの条件について説明します。
その1 安定した収入と貯蓄
まず何より重要なのが経済的に自立していることです。夫やパートナーからの金銭的援助や養育費を当てにしない以上、自分の収入だけで子どもを育て上げる覚悟と能力が必要になります。厚労省の調査によれば、未婚の母子世帯の平均年間収入(世帯収入)は約454万円です。
もちろん生活コストは住む地域やライフスタイルによって変わりますが、最低でもこれくらいの収入があればひとまず子育てはやっていけるとされています。できればそれ以上に稼ぎ、日頃から十分な貯蓄をしておくことが望ましいでしょう。
具体的には、正社員として安定した職を得るか、高収入の職種に就くなどして継続的な収入源を確保することが大切です。育児に備えて産前にできるだけ貯金を増やし、育休中や子どもが小さいうちの収入減少に耐えられる蓄えを作っておくのが理想です。
また、ベビーシッターや家事代行サービスを利用するにもお金がかかりますから、そうした外部サポートを活用できるだけの余裕資金も考慮しましょう。公的支援も利用できますが、支給には所得制限があるため、高収入である程度やっていけるなら公的手当てには頼らずに済む場合もあります。「自分と子どもの生活は自分で支える」という強い意志と現実的な年収が、まず第一の条件です。
その2 精神的な覚悟と強い意志
二つ目の条件は、精神的に自立していることです。選択的シングルマザーを選ぶ以上、周囲からの偏見や批判に動じない強い心が求められます。世間には先述の通り様々な否定的意見がありますが、そうした声に振り回されず「自分が決めた道で我が子と二人幸せに暮らすんだ」という確固たる覚悟が必要です。
子育てはただでさえ忍耐や努力を要するものですが、シングルで臨む場合はなおさらです。深夜に子どもが泣き止まなかったり、自分が疲れ果ててしまったとき、「なんで私一人で頑張っているんだろう…」と弱気になる瞬間が訪れるかもしれません。
そのような時でも、「この子の未来のために」「自分で選んだ道だから」という信念を持って踏ん張れる精神力が不可欠です。母親の心が後から揺らいでしまうと、子どもも不安定になり、親子ともに不幸せな状況に陥りかねません。そうならないためにも、強い意志とポジティブな思考で困難を乗り越える覚悟を事前に固めておきましょう。
また、自分の選択に誇りを持つことも大切です。「結婚しないで子どもを産むなんて…」という世間の古い価値観に引きずられず、「これも自分らしい家族の形だ」と胸を張ることができれば、周囲の雑音に悩まされることも減ります。
その3 周囲の協力体制とリスクへの備え
三つ目の条件は、万が一に備えたリスクヘッジと周囲の協力体制づくりです。人間誰しも病気や事故に遭う可能性があり、シングルマザーにももしもの事態は起こりえます。長期的な視点で、自分に万が一のことがあっても子どもの安全や健康、生活が脅かされないよう事前に手を打っておくことが重要です。
具体的には、まず生命保険や医療保険に加入しておき、自分に何かあった場合に子どもが経済的に困窮しない準備をしましょう。信頼できる親族や友人にあらかじめ事情を説明し、緊急時には子どもの面倒をお願いできるような関係を築いておくことも有効です。
普段から親や兄弟姉妹、親友などと密にコミュニケーションをとり、いざというときサポートを頼みやすい環境を整えておくと安心です。シングルマザー同志のコミュニティや支援団体に加入して情報共有したり、助け合えるネットワークを持つことも心強いでしょう。
また、子どもの将来のために公正証書や遺言を準備し、万一自分に何かあった際の後見人や財産管理について決めておくのもリスク対策の一つです。これは縁起でもない想定かもしれませんが、母親一人が親権者である以上、自分に何か起きた時の子どもの人生も考えておく責任があると言えます。備えあれば憂いなしというように、十分なリスクヘッジを施しておけば日頃の生活にも余裕が生まれます。
最後に、行政の支援制度についても調べて活用することが大切です。自治体によってはひとり親家庭向けの児童扶養手当、水道料金減免、医療費助成、保育料補助など様々な支援があります。居住地の子育て支援窓口に相談したり、制度が充実している地域への引っ越しを検討するのも一案でしょう。こうした公的支援や地域の子育てサービスを上手に利用する知識も身につけ、「困ったときはお互い様」と周囲に頼る準備を整えておくことが、長く安定して子育てを続ける鍵となります。
選択的シングルマザーになると後悔するのか?
人生の重大な選択をするとき、「後悔しないだろうか?」という不安はつきものです。選択的シングルマザーの場合も、「一人で子育てして後悔しないかな…」と悩む方は多いでしょう。結論から言えば、十分な準備と覚悟を持ってこの道を選べば、後悔する可能性は低いと考えられます。
大切なのは、事前にデメリットや困難をしっかり理解した上で決断することです。子どもを産むかどうかは人生を左右する重大な判断であり、それ相応の覚悟が必要です。厚生労働省の調査記事でも「子供を出産してから後悔しないよう、デメリットもしっかり把握してから選択的シングルマザーになるか決めましょう」と強調されています。
言い換えれば、想定される苦労やリスクを理解した上で「それでも私はこの道を行く」と決めたのであれば、後になって「こんなはずじゃなかった…」と嘆く可能性は低くなるということです。
実際に選択的シングルマザーとして子育てしている人たちの声を見ても、「後悔している」という意見はあまり多くありません。むしろ、「忙しいし大変なことも多いけれど、それ以上にかけがえのない喜びがある」といった前向きな声が目立ちます。例えば、40代で未婚出産を選んだ大学教員の女性は、「娘が生まれてからの日々は苦労も多いけれど、それ以上にかけがえのない喜びに満ちています。あの時、人生が変わるほどの決断をした自分に感謝しています」と語っています。彼女は「この道を選んだことに全く後悔はなく、『過去の自分ナイス!』と思っている」とまで言い切っており、シングルマザーの道を選んだ自分自身を誇りに感じています。
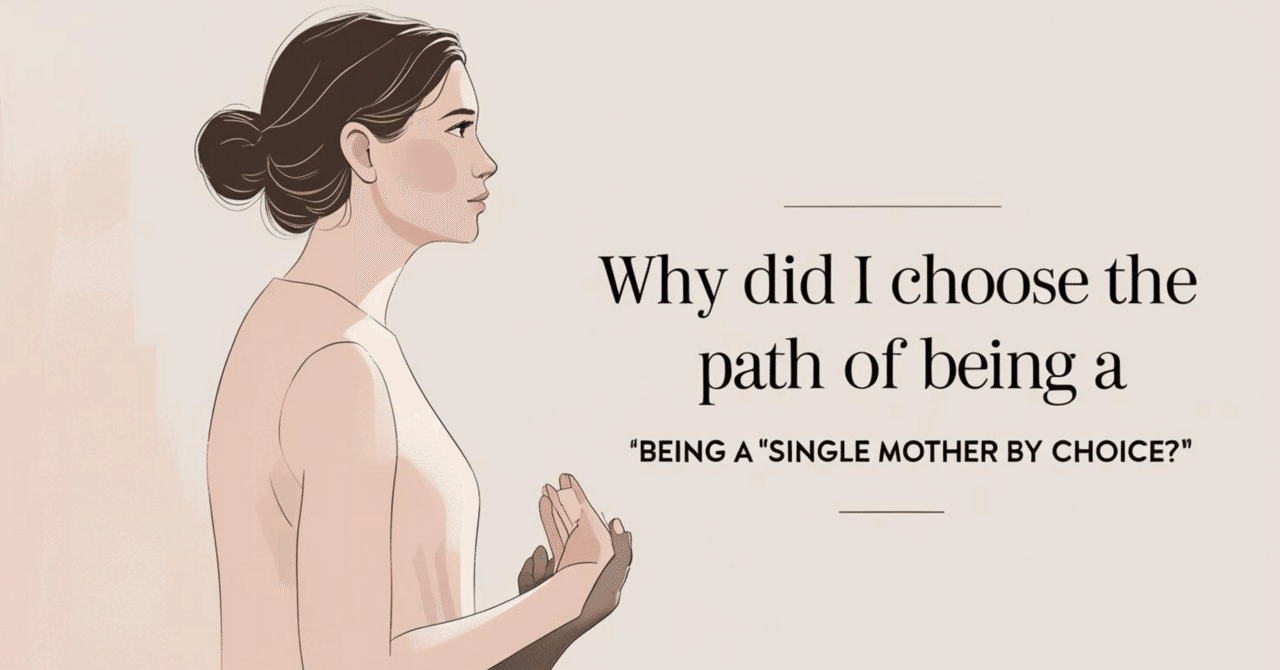
もちろん、全く悩みがないわけではありません。一人で子育てしていれば、「今日はクタクタでもう限界…」という日だってありますし、ふと「もし結婚していたらもっと楽だったのかな」と頭をよぎる瞬間がゼロとは言い切れません。それでも、「自分が望んで選んだ人生だ」という軸さえブレなければ、一時的に大変さを嘆くことはあっても深刻な後悔には繋がりにくいでしょう。むしろ子どもの成長する姿や笑顔を見るたび、「この子を産んで本当に良かった」と実感が上回るはずです。先の女性も「ときには疲れ果てて自問することもある。でも『この子の未来のために』という思いがエネルギーになる」と述べています。辛さより喜びが勝るからこそ、多くの選択的シングルマザーは後悔せず頑張れているのです。
究極的に言えば、選択的シングルマザーになることが後悔をもたらすのではなく、なった後の生き方が後悔の有無を左右するのです。
選択的シングルマザーという価値観の是非
では最後に、選択的シングルマザーという価値観は是か非かについて考えてみます。これは突き詰めると、「結婚せずに子どもを持つ」という生き方を社会が認めるべきか、個人として良しとするかどうか、という問いです。
結論から言えば、この価値観自体に善悪のレッテルを貼るべきではないでしょう。子どもを持つかどうか、持つとしたらどのような形で育てるかは、本来ひとりひとりの人生観に基づく自己決定の問題です。
国際的にも「子どもを産むか産まないかを決める権利は女性本人にある」というリプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)の考え方が広く認識されています。多くの日本人女性は「子どもを持つかどうかは自分だけで決めていいものではない」と考えがちですが、それは必ずしも世界標準ではありません。自分の意思で母になることも、結婚・出産しない人生を選ぶことも、本来は当事者の女性自身が決めて良いはずのことなのです。
「子どもの権利は?」という議論もありますが、そこもバランス感覚が必要です。確かに子どもの視点からすれば、生まれながらに父親がいない状況には後から疑問を抱くかもしれません。その点は先述した「出自を知る権利」への配慮など、子どもの心情に寄り添った対応が親には求められます。
例えば、精子提供で生まれた子の場合、可能な限り情報を開示してあげるとか、父親がいないことをネガティブに感じさせないよう十分な愛情と教育を与えることが大切です。「お父さんはいないけどあなたは愛されて生まれてきたんだ」というメッセージを伝え、子どもが自尊心を持てるよう育てるのは親の責任でしょう。その責任を果たす覚悟があるなら、他人がとやかく批判する筋合いではありません。
社会全体として見ると、家族のかたちは時代とともに多様化しています。ひと昔前にはシングルマザー自体が珍しかったのが、今では離婚やシングルマザーも特別なことではなくなりました。同様に、未婚で母になる選択も今後増えていく可能性があります。選択的シングルマザーという価値観も、その新しい家族像の一つと言えるでしょう。
むしろ問題なのは、社会の側の体制や意識が追いついていないことです。児童扶養手当などの制度はあるものの、未婚のひとり親に対する偏見は根強く、十分な支援が行き届いているとは言えません。
つまり、価値観の是非というより、選択的シングルマザーが安心して暮らせる社会かどうかが問われているのです。
総合的に見て、選択的シングルマザーという生き方は本人の状況と覚悟次第では十分に尊重されるべき選択肢です。もちろん、全員に勧められる道ではありません。経済的・精神的負担は大きく、誰もが容易に真似できるものではないでしょう。
しかし、自分の人生観に照らして「結婚は望まないが子どもは授かりたい」という強い希望があり、それを支える力と意志がある人にとっては、有意義な人生の形となり得ます。現代は多様性の時代です。他人の家族の形に対し、古い常識だけで「正しい」「おかしい」と決めつけるのではなく、当事者と子どもが幸福であるかを基準に捉え直すべきではないでしょうか。
まとめ:家族の在り方を考える
選択的シングルマザーについて、その定義から批判される理由、必要な条件、後悔の有無、価値観の妥当性まで見てきました。結論として言えるのは、「頭おかしい」と批判されるような異常なことでは決してないということです。
確かに、父親不在や経済的不安など課題はありますが、それらは本人の努力と周囲の支援次第で克服できるものです。むしろ、そうした選択をせざるを得ない状況に追い込まれる女性たちを孤立させている社会環境こそ見直す必要があります。
家族のかたちは多様であり、何が幸せかも人それぞれです。大事なのは、どんな形であれ親と子が愛情をもって支え合い、社会もそれを支えることではないでしょうか。従来の結婚観・家族観にとらわれず、自分にとって最良の生き方を選ぶ女性が増えているのは、時代の流れとも言えます。選択的シングルマザーという選択肢も、その一つとして尊重されるべきでしょう。
もちろん、誰もが簡単に選べる道ではありません。選択的シングルマザーになるには経済力や覚悟が求められ、社会のサポートも不可欠です。しかし、それらが整っているならば、一人でも子どもを育てたいという母親の願いは真剣に受け止められて良いはずです。世間の目に惑わされず、本人と子どもが幸せである道なら、それがその家族の正解なのではないでしょうか。
【参考資料】
- 厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果」media.withwork.comwoman.mynavi.jp
- 厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査」media.withwork.com
- 子どものこころ専門医・坂野真理氏による解説記事s-iiyo.coms-iiyo.com
- 弁護士法人あおい法律事務所 離婚コラムaoilaw.or.jpaoilaw.or.jp
- withwork Magazine 選択的シングルマザー解説記事media.withwork.commedia.withwork.commedia.withwork.com
- マイナビウーマン 記事「選択的シングルマザーって実現可能?お金の面から考えてみた」woman.mynavi.jpwoman.mynavi.jp
- Asahi新聞(かがみよかがみ)渥美志保氏の記事mi-mollet.commi-mollet.com
- 選択的シングルマザー当事者の体験談(note)note.comnote.com











コメント