配偶者と死別してシングルマザーになることは、深い悲しみとともに突然多くの責任を抱える辛い状況です。愛する人を失った悲嘆に向き合いながら、育児や家事、仕事を一人でこなさなければならず、心身ともに疲れ切ってしまうこともあるでしょう。
それは決して珍しいことではなく、多くのシングルマザーが一度は感じる悩みでもあります。大切なのは、自分だけで全てを背負い込まないことです。「母親だから弱音を吐いてはいけない」という思い込みを捨てて、必要なときには周囲や専門家の力を借りることが、あなたとお子さんの幸せにつながります。
この記事では、死別によってシングルマザーになった方が心身ともに「疲れた…」と感じたときに、ぜひ試してほしい5つの対処法を紹介します。一人で抱え込まず、少しでも心と体を楽にするヒントにしてみてください。
死別でシングルマザーになる人の数
まず最初に、同じ境遇の人がどれくらいいるのか知っておきましょう。日本のひとり親世帯全体の中で、配偶者との死別が理由でシングルマザーになった世帯は約5.3%とされています。
これは令和3年度(2021年)の厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」によるデータで、前回調査(平成28年度)の8.0%から割合は減少しています。
割合だけ見ると多くないように感じますが、母子世帯全体の母数が約119.5万世帯と膨大なため、実数にすると約6.3万世帯ものシングルマザーが配偶者と死別を経験していることになります。
なお、シングルファザーの場合は約21%が死別によるひとり親世帯となっており、母子世帯より高い割合となっています。
死別でシングルマザーになった人が疲れたときにすべき5つのこと
大切な人を亡くし、慣れないひとり親生活に奮闘するうちに疲れが限界に達してしまうのは、ごく自然なことです。ここからは、疲れを感じたときに試してほしい5つの対策を紹介します。一つひとつはシンプルですが、ぜひできるところから取り入れてみてください。
その1: 十分な休息と睡眠を取り、頑張りすぎない
まず何よりも意識してほしいのは、しっかり休むことです。育児や家事に仕事まで一人で抱えるシングルマザーの生活は常に時間との戦いで、知らず知らずのうちに慢性的な睡眠不足・休息不足に陥りがちです。休みたくても休めない日々が続くと疲労が蓄積し、心身の不調を招きかねません。
「無理をしない」ことは決して甘えではなく、長く子育てを続けていくための戦略です。たとえば「今日は家事を少しサボって早く寝る」「週末は掃除より自分の休養を優先する」といったように、意識的に休息時間を確保しましょう。
どうしても自分一人では休む暇がない場合は、身近な人に協力をお願いしてでも睡眠時間を確保することが大切です。家族や信頼できる人に数時間子どもを見てもらい、その間にゆっくり眠るだけでも体力・気力の回復につながります。疲れ切って倒れてしまっては元も子もありません。
「頑張りすぎない勇気」を持ち、定期的に自分を労わる時間を取るようにしてください。
その2: 一人で抱え込まずに周囲に相談する
配偶者を亡くして間もない頃は特に、「私がしっかりしなければ」と気丈に振る舞おうとしてしまいがちです。しかし、孤軍奮闘する必要はまったくありません。困ったときは遠慮なく周囲に頼り、相談することが何より重要です。
周囲に相談できそうな身近な人がいれば、まずは思い切って頼ってみましょう。親や兄弟姉妹、仲の良い友人など、あなたを心配している人はきっといるはずです。「弱音を吐いたら迷惑かな…」と遠慮する必要はありません。あなたが疲れて辛い思いをしていると知れば、家事の手伝いや育児のフォローなどできる範囲で助けてくれる人は必ずいます。
身近に頼れる人がいない場合も、孤独を感じる必要はありません。各自治体にはひとり親家庭の総合相談窓口が設置されています。都道府県や政令指定都市には「母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親家庭支援センター)」があり、生活や子育て、仕事、法律問題まで含めてワンストップで相談に乗ってくれます。電話やメールで相談できるNPOのホットラインも存在します。
例えば、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむの無料相談では、「ママが元気になれば子どももしあわせに!」を合言葉に、親身に話を聞いてもらえるといいます。行政の窓口や支援団体の相談員は、あなたとお子さんを支えるプロです。決して一人で悩まず、「助けてほしい」と声を上げてください。
その3: 行政や各種支援サービスを積極的に活用する
シングルマザーを支えるために、国や自治体にはさまざまな支援制度やサービスが用意されています。それらを遠慮せずフル活用することも、疲れを軽減する大きなポイントです。
「忙しくて調べる時間がない」「手続きが面倒そう」と敬遠しがちかもしれませんが、知らなければ損をする有用な制度がたくさんあります。
例えば、自治体によっては育児や家事を手伝ってくれるヘルパー派遣を行っています。豊島区の「育児支援ヘルパー事業」のように、ひとり親家庭になった直後や親の体調不良・就職活動時に、家庭にヘルパーを派遣して育児・家事をサポートしてくれる制度もあります。
また、全国の市区町村で共通して実施されているのが一時的な子どもの預かりサービスです。具体的には、自治体の子育て支援事業として、「短期入所生活援助(ショートステイ)」「夜間短期託児(トワイライトステイ)」などと呼ばれるものがあります。
これは、親御さんが病気や仕事、そして「育児疲れ」などで一時的に子どもの養育が困難となった場合に、子どもを施設で短期間預かってもらえる制度です。例えばショートステイなら数日〜1週間程度、専門の児童養護施設等で子どもを宿泊で預かってもらえます。
実際、東京都小平市では「子育てに疲れてしまった。少し休みたい」という時に利用できる一時預かりサービスが案内されています。宿泊はできない日中の一時保育であっても、子どもを安心して預けられる場所があるだけで心に余裕が生まれます。
その4: 同じ境遇のシングルマザーと繋がり悩みを共有する
孤独感や不安を感じたときには、自分と同じ境遇の仲間と繋がることも大きな助けになります。周囲にシングルマザーの友人がいない場合でも、今は地域やオンラインでひとり親同士が交流できる場がいろいろと用意されています。
日本シングルマザー支援協会の江成道子代表理事も「周りに相談できる人がいないということですが、自分と同じ境遇の人たちが集まるコミュニティを探してみましょう」とアドバイスしています。特に、シングルマザー同士で収入や生活環境が近い人々と知り合えると、お互い余計な気遣いなく本音で話せるので良い息抜きの場になります。
具体的には、自治体や支援団体主催のひとり親の交流イベントに参加してみるのも一案です。男女共同参画センターなどが開催するシングルマザー・シングルファザーの集まりに顔を出してみれば、「仲間ができて嬉しかったです」という利用者の声が聞かれるように、同じ悩みを共有できる心強い友人が見つかるかもしれません。
インターネット上にもシングルマザー同士が悩みを相談し合えるコミュニティやSNSグループが存在します。ただしネットの場合は玉石混交なので、公的機関や信用できる団体が運営するものを活用すると安心です。同じ立場の仲間がいると思えるだけで、孤独感や不安は和らぎます。お互いの体験談や知恵を共有することで、「自分だけじゃないんだ」と前向きな気持ちを取り戻せるでしょう。
その5: 必要に応じて専門家に相談し心のケアをする
忙しさに追われて自分の気持ちを後回しにしがちですが、心の健康にも目を向けることが大切です。悲しみやストレスを一人で抱え込み、心が疲弊してしまう前に、専門家の力を借りることをためらわないでください。
もし夜眠れない日が続いたり、常に不安やイライラに襲われて気持ちが沈み込んでしまうようなら、それは心と体からの「休んで」「助けて」というサインです。
「育児中は自分の時間が取れず病院に行きづらい」と考えるママは多いですが、家族や周囲の協力を得てでも早めに専門医に相談することが重要です。心療内科や精神科だけでなく、自治体の子育て相談窓口でカウンセリングサービスを紹介してもらえる場合もあります。
また、配偶者との死別という同じ経験を持つ人々が集まり、お互いの気持ちを分かち合う「グリーフケア」の会も各地で開催されています。専門のカウンセラーや臨床心理士が同席して話を聞いてくれる場もありますので、必要に応じて活用してみてください。
「母親なんだから弱音を見せてはいけない」と自分を追い込む必要はありません。むしろ、自分の心が満たされていないと子どもを幸せにすることはできないと思うべきです。カウンセラーに思い切り愚痴を吐き出したり、時には泣いたりすることで心が軽くなるなら、遠慮なくその時間を確保しましょう。
心身の不調は放置すると長引いてしまいます。専門家の手を借りるのは決して恥ずかしいことではなく、あなたとお子さんの笑顔を守る賢い選択なのです。
必ず助けてくれる人はいる
ここまで述べてきたように、世の中にはあなたを助けたいと思っている人や制度が必ず存在します。それは決して大げさな希望的観測ではありません。事実、行政から民間まで幅広い支援の網があなたの周りに張り巡らされており、手を伸ばせば届くところにあります。大切なのは「助けが欲しい」と声に出すこと、そして差し伸べられた手を掴む勇気です。
配偶者を亡くし途方に暮れているとき、優しく励ましてくれる家族や友人がいるかもしれません。もし身近にいなくても、全国には同じ経験をしたシングルマザー・シングルファザーたちがおり、支え合うネットワークが存在します。
行政の窓口にはあなたとお子さんのために親身に話を聞き、一緒に解決策を考えてくれる相談員が待機しています。NPO法人や支援団体のスタッフも、あなたが一歩踏み出すのを待っています。
例えば、前述のしんぐるまざあず・ふぉーらむのホットラインに電話相談した方は、「ひとりじゃないと実感しとても心強かった」と語っています。あなたが勇気を出して声を上げれば、思いもよらないところから支援の手が差し伸べられることもあります。
「必ず助けてくれる人はいる」という言葉を信じてください。それは決して綺麗事ではなく、これまで多くのひとり親たちが実感してきた現実です。孤立しているように感じる夜もあるかもしれません。しかし、日本中にあなたとお子さんのことを案じ、力になりたいと願っている人々がいることを忘れないでください。あなたは一人ではありません。必要なときにはいつでも、周囲に助けを求めていいのです。
一人で抱え込まず支援を求めよう
配偶者との死別を乗り越え、子育てと生活を両立していくのは並大抵の苦労ではありません。その中で「疲れた」「もう限界かも」と感じるのは当然のことです。そんなときこそ思い出してほしいのが、「一人で抱え込まなくていい」ということ、そして「周りには頼れる支援がたくさんある」ということです。
本記事で紹介したように、十分な休息を取ることから始まり、周囲への相談、公的サービスの活用、仲間との交流、専門家の力を借りることまで、あなたの疲れを和らげるための手段は数多く存在します。
最後に、どうか自分自身を責めないでください。十分に頑張っている自分を認め、労わってあげましょう。お母さんが笑顔を取り戻すことは、お子さんの幸せにも直結します。一人で泣きたい夜には、そっと誰かに頼ってみてください。
あなたとお子さんが笑顔で歩んでいけるよう、社会は様々な形であなたを支えています。勇気を出してその支援の手を掴み、決して一人ではないことを実感しながら、無理のない歩幅で前に進んでいきましょう。あなたの頑張りを、そしてあなた自身の幸せを、心から応援しています。

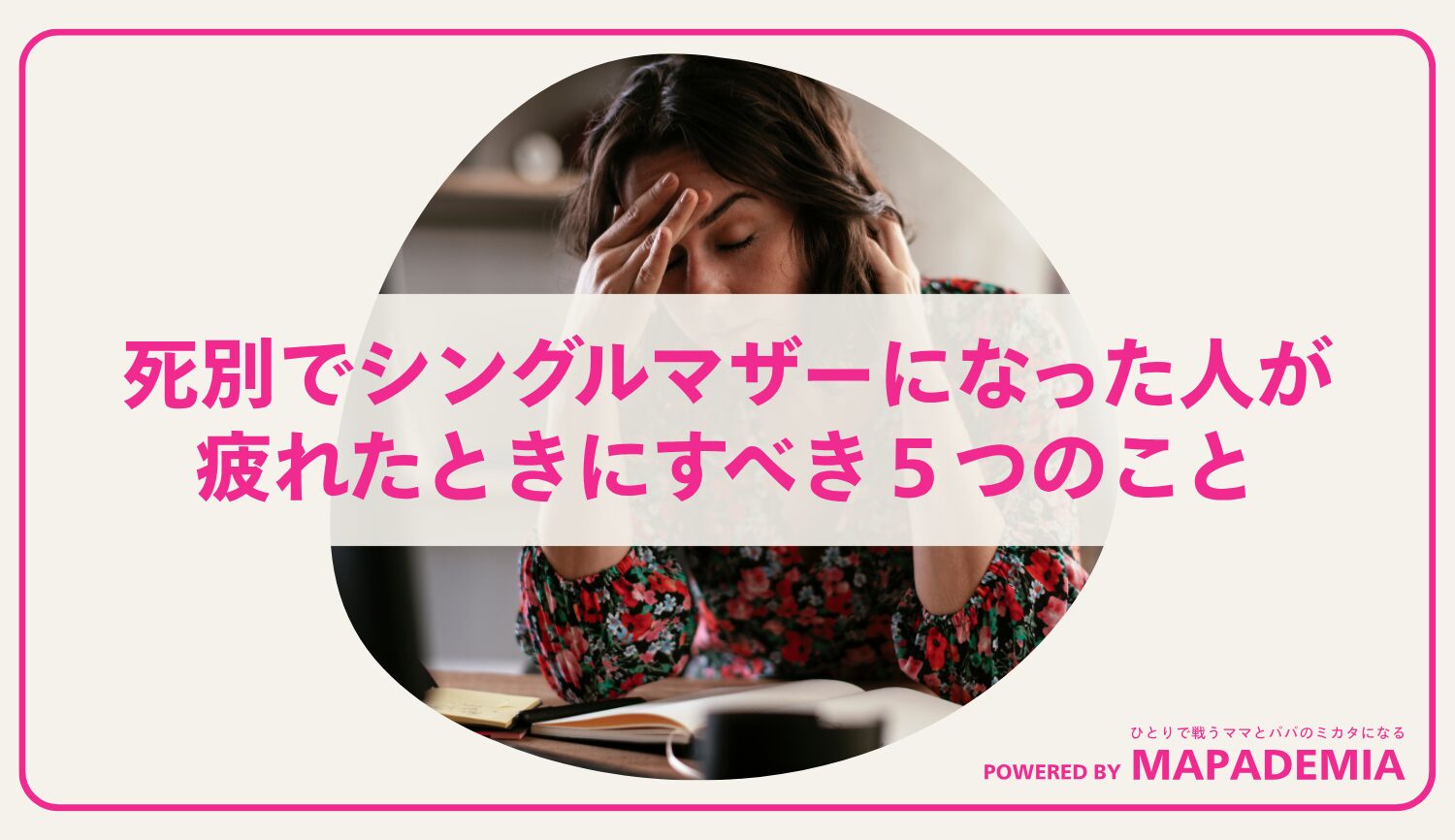










コメント