「シングルマザーとは関わりたくない」といった声を耳にすることがあります。日本には約120万世帯もの母子家庭(シングルマザー世帯)が存在し、多くの母親たちが仕事と育児を懸命に両立させています。
しかし一方で、シングルマザーに対する根強い偏見や否定的な見方も残っています。なぜ人々はシングルマザーを敬遠したり、偏見の目で見てしまうのでしょうか?
本記事では、「シングルマザーと関わりたくない」と言われる主な理由と、その偏見が生まれる背景について詳しく解説します。
「シングルマザーと関わりたくない」と言う理由
シングルマザーに対して否定的な感情を抱く人は、一体どのような理由で「関わりたくない」と感じているのでしょうか。ここでは、よく挙げられる3つの理由を説明します。
理由1: 行政の手当で遊んで暮らしているという偏見
まず挙がるのが、「シングルマザーは税金による手当をもらって楽をしている」という偏見です。離婚や未婚で母子家庭になった女性に対して、「自分の選択でシングルマザーになったのに、行政の支援に甘えて遊んで暮らしているのは許せない」という反感を抱く人がいます。
実際、「働けるのに働かず生活保護をもらって当たり前と思っているなんてふざけるな」といった批判的な声もインターネット上で見られます。
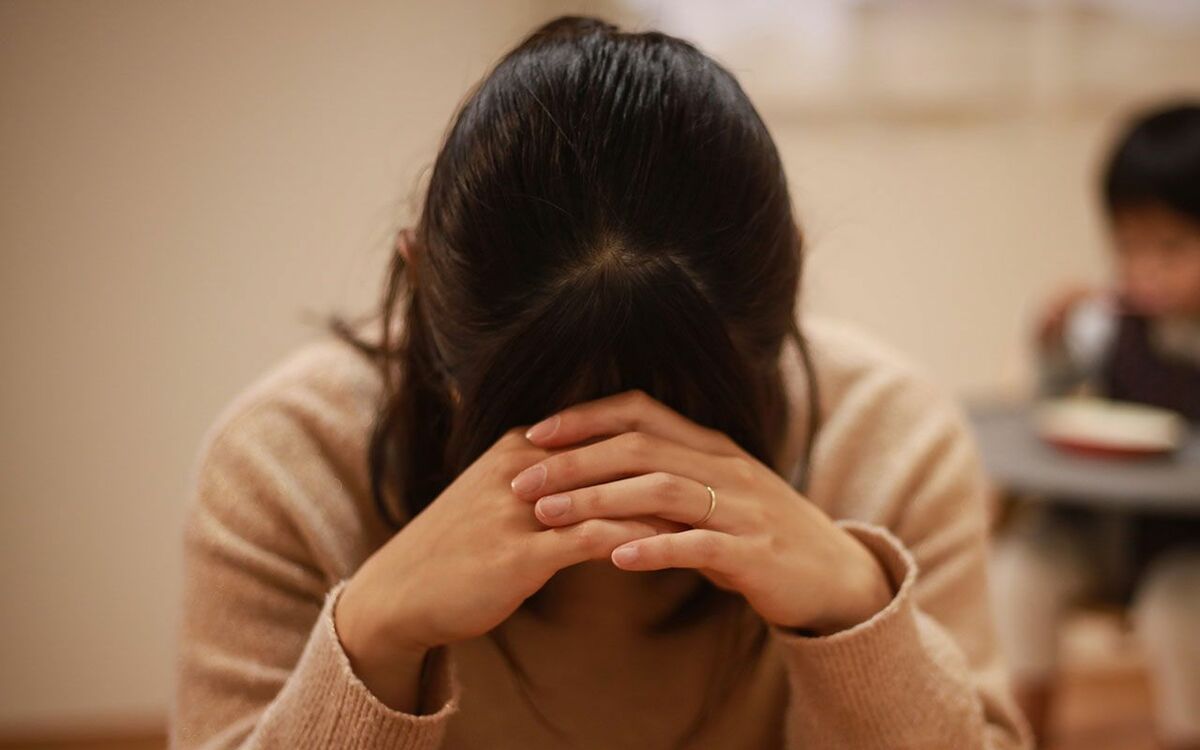
しかし、これは事実に基づいた一般像ではなく偏見に過ぎません。厚生労働省の調査によれば、令和元年時点で生活保護を受給している母子世帯は約7万5千世帯で、2012年度の約11万4千世帯をピークに減少傾向にあります。
シングルマザー世帯全体(約120万世帯)から見れば生活保護に頼っている家庭は一部であり、多くの母親たちは貧困から抜け出すため懸命に働いています。むしろ「遊んで暮らすシングルマザー」というイメージが先行し、実態以上に偏見が広がっているのが現状です。
理由2: 何でも「被害者ぶっている」という反発
二つ目の理由は、「シングルマザーは自分の大変さをアピールしすぎる」という周囲の反発です。
自ら結婚や出産、離婚を選択したにもかかわらず、「私ひとりで子育てして大変」「シングルマザーだから仕方ない」といった苦労アピールをされると、周囲は「被害者ぶるな」と冷ややかな気持ちになることがあります。
確かにシングルマザーが家事・育児・仕事を一人でこなす大変さは想像に難くありません。しかし、「シングルマザーだから大変なんだ」と過度に周囲へ訴える態度は、「どの家庭だって苦労はあるのに…」と反感を招きかねません。
事実、「皆それぞれ大変なのに、悲劇のヒロイン気取りで愚痴をこぼす一部の人は正直関わりたくない」という意見も見られます。シングルマザーに限った話ではありませんが、常にネガティブな愚痴や不幸話を聞かされると周囲もうんざりし、距離を置きたくなるものです。
このように「被害者意識が強い」「甘えている」というレッテルは、多くの場合偏見に基づいています。実際には、大半のシングルマザーは周囲に迷惑をかけまいと必死に踏ん張っており、自ら進んで不幸をひけらかしているわけではありません。それでも「大変アピール」に見えてしまうのは、シングルマザーへの理解が十分でないがゆえの誤解と言えるでしょう。
理由3: モラルや生活態度への否定的イメージ
三つ目の理由は、シングルマザー本人の人間性や家庭環境に対する偏見です。例えば「シングルマザーになるような人はだらしない」「家庭が崩壊するのは本人に問題があるからだ」といったネガティブなイメージが根強くあります。
実際、未婚の母に対して周囲から「シングルマザーはだらしない」という誤解混じりの偏見の目が向けられることがあり、本人に大きな精神的負担を与えています。離婚や未婚でシングルマザーになった女性に対し、「何か人間的な欠陥があるのではないか」「男性を繋ぎとめられない奔放な性格ではないか」と勝手なレッテル貼りをする向きもあります。さらに、「母子家庭の子どもは可哀想」「グレやすい」といった子どもに対する偏見も含め、母子家庭全体を下に見るような風潮も存在します。
しかし、これらのイメージもまた事実とは異なります。例えば「母子家庭の子は非行に走りやすい」という俗説について医学的根拠はなく、むしろ経済的困難や親のストレスといった環境要因の方が影響すると指摘しています。
子どもの健全な発達に関して「ひとり親家庭であること自体は問題に直結しない」ことは厚生労働白書でも明示されており、家庭形態そのものより周囲の支えや環境の方が重要なのです。シングルマザー本人についても、「だらしない」「非常識」といった偏見は思い込みに過ぎず、多くの母親たちは子どものために責任感を持って努力しています。否定的なイメージだけで人物像を決めつけるのは、偏見以外の何ものでもありません。
シングルマザーに対する偏見が生まれるのはなぜ?
以上のような「シングルマザーと関わりたくない」と思わせる偏見の裏には、どのような背景や原因があるのでしょうか。ここからは、シングルマザーに対する偏見が生まれる主な原因を3つ考察します。
原因1: 「標準家族」から外れた女性への文化的な偏見
日本社会には伝統的に「標準世帯=父母と子」という家族観が根強くありました。そのため、このモデルから外れる母子家庭に対しては、長年にわたり負のイメージが付きまとってきました。高度経済成長期以降、「母子家庭の子は非行に走りやすい」「シングルマザーになったのは自己責任だ」といった偏見がメディアで語られることもあり、未婚の母や離婚女性に対する見えない圧力が残ったのです。実際、未婚で子どもを産んだ女性が職場や地域で肩身の狭い思いをしたり、離婚歴を明かした途端に周囲の態度が変わる――そんな話も耳にします。
また、性別役割に根差した差別意識も偏見の背景にあります。シングルファーザーに対しては「男手一つで偉いですね」と同情や称賛の眼差しが向けられることが多い一方、シングルマザーには厳しい視線が注がれがちだと指摘されています。
これはシングルマザーへの根強い性差別的な見方の裏返しとも言えます。つまり、「母親は本来家庭を守るべきなのに、それができないのは本人に問題がある」という無意識の偏見です。近年こうした風潮は少しずつ是正され始めていますが、それでも米ワシントン・ポスト紙が「日本ではシングルマザーたちは貧困と『恥の文化』と闘っている」と報じるほど、根底には古い家族観に基づく偏見が残存しています。


原因2: 強い自己責任論と支援制度への誤解
偏見が生まれる二つ目の要因は、「貧困も苦労もすべて自己責任だ」という風潮と、シングルマザー支援に関する誤解です。日本では自己責任論が根強く、離婚やシングルマザーになったのも本人の選択なのだから、その後の生活苦も本人の責任だと考える人が少なくありません。
実際、ネット上には「勝手に離婚したんだから国のせいにするな」「シングルマザーの貧困は自業自得」というような厳しい声も見られます。こうした極端な自己責任論は、シングルマザーへの冷たい視線を生み出す一因となっています。
さらに、その自己責任論と結びついて、「シングルマザーは散々税金の援助を受けているくせに何を言っているんだ」という誤解も偏見を助長します。
シングルマザーの貧困や孤立は本人だけの責任で片付けられる問題ではなく、低賃金や雇用環境、社会的な偏見など構造的な要因が大きいのです。支援制度について正しい理解が広まっていないことや、自己責任論が独り歩きしていることが、シングルマザーへの偏見を生む温床になっています。
原因3: 社会のストレスと「弱者叩き」の心理
三つ目の原因として、現代社会における人々のストレスや不満のはけ口という側面が挙げられます。不景気や生活の不安が広がる中で、多くの人が心に余裕を失いがちです。
その結果、自分より弱い立場に見える相手を攻撃することで鬱憤を晴らし、優位に立ったような安心感を得ようとする心理が働く場合があります。実際、日本人は「普通でいたい」思いが強いため、マイノリティー(少数派)を差別することで安心感を抱きがちだと指摘する専門家もいます。
シングルマザーはまさに伝統的な“普通の家庭”から外れた存在であり、不満や怒りの矛先にされやすい弱者層と言えるでしょう。
近年、SNSやネット掲示板では生活保護受給者や貧困層、母子家庭に対する心ないバッシングが目立っています。例えば、全国のひとり親家庭の困窮状況に関する調査結果が報じられた際には、「米も買えないなんて嘘だ」「補助金もらってるくせに文句言うな」「そんな親に子育てする資格ない」等、数え切れないほどの罵詈雑言がSNS上にあふれ、大炎上しました。
本来であれば「物価高で苦しんでいる家庭もあるのだな」と共感や想像を働かせるべきところが、そうした想像力は欠如し、「黙れ!」「嘘つき!」といった攻撃的な反応に直結してしまったのです。ここには、日本社会全体の共感力の欠如や不寛容さが垣間見えます。自分自身も余裕がないために、他者の苦境に思いを馳せることができず、逆にその弱さを責め立ててしまう――そんな心理が偏見を生む土壌になっているのです。
生活への不満が他者の非難になる
「生活に余裕がない」と感じる人が増えると、その不満が他者への非難に転化しやすくなります。自分もつらい思いをしていると、「あの人ばかり優遇されてずるい」「自分だって我慢しているのに、なぜ助けを求めるのか」といった歪んだ感情が芽生えやすくなるのです。
特にシングルマザーのように支援を受けている人々は、嫉妬や誤解の対象になりがちです。「苦しいのは皆同じなのに、自分だけ大変だと言うな」「ちゃんとやりくりすれば生活できるはずだ」という厳しい意見の裏には、その人自身の鬱屈した不満が透けて見える場合があります。
さらに、現代の日本社会は他者に共感し寄り添う余裕を失いつつあるとも言われます。健康社会学者の河合薫氏は、日本が平然と弱者を叩く“不寛容社会”になっている現状に警鐘を鳴らしています。彼女は著書の中で、困窮するひとり親家庭への激しいバッシングを例に挙げ、「和(調和)も思いやりもない社会では、ちょっとしたことで『自己責任だ』『怠けている』と非難の声が上がる」と指摘します。
その背景には、各個人が抱える将来不安や生きづらさがあるのでしょう。自分の生活が精一杯で心に余裕がないと、他人を思いやるより批判する方が手っ取り早い発散法になってしまうのです。
このように、生活への不満や社会的ストレスが高まると、それが弱者への偏見や非難となって現れる傾向があります。シングルマザーに向けられる厳しい言葉の数々も、見方を変えれば、余裕を失った人々の悲鳴なのかもしれません。本来であれば支え合うべきところを、互いに叩き合ってしまう――そんな不寛容な風潮そのものが、実は社会全体の危機といえるでしょう。
まとめ:余裕のない社会になっている?
以上の考察から浮かび上がるのは、私たちの社会が徐々に「心の余裕を失った社会」になりつつあるのではないかという疑問です。シングルマザーに対する偏見の数々は、その多くが事実というより思い込みや誤解に基づいていました。
では、なぜそれほどまでに人々は偏見を募らせてしまうのでしょうか?
おそらく、その背景には、自分の生活で手一杯なあまり他者への思いやりを持てない社会状況や、競争・自己責任を強調する風潮があるのかもしれません。
余裕のない社会は誰にとっても生き辛いものです。他者を非難する前に、その人の置かれた状況や努力に思いを馳せてみる――そんな小さな心がけが、偏見を和らげる第一歩になるでしょう。シングルマザーへの偏見の背景には社会全体の問題が潜んでいます。
だからこそ社会全体で支え合い、誰もが余裕を持って暮らせる環境を取り戻すことが大切です。偏見や差別のない包摂的な社会を目指し、私たち一人ひとりが正しい理解と共感の輪を広げていきましょう。











コメント