本記事では、みてねのアルバムを両家別々にするメリットとデメリットを圧倒的な情報量で丁寧に解説し、両家一緒にする場合との比較を行います。それぞれの方法を採用した家庭の実例を交えながら、どちらが自分たちにとって最適か判断するヒントを提供します。最後に、家族間で円満に利用するためのルール作りについてもアドバイスします。それでは詳しく見ていきましょう。
みてねを両家別々にするメリット
両家の祖父母でアルバムを別々に分けることには3つのメリットがあります。
ここからは、その主な理由を順番に説明します。
メリット1: プライバシーを確保し、見せたくない写真も安心して共有できる
みてねのアルバムを両家で分けておけば、公開範囲を家族ごとに限定できるためプライバシーを保護できます。例えば、ある側の親戚と一緒に写っている写真や、自宅の生活感が映り込んだ写真など、「相手の実家には見せづらい…」と感じる部分もあるでしょう。
アルバムを別々にしておけば、自分の実家向けアルバムにはそういった写真も気兼ねなくアップでき、義実家には見せたくないものは見せずに済むわけです。
具体的には、筆者の家庭では妻側アルバムには撮った写真を全てアップし、夫側アルバムには背景に気を遣わなくて済む厳選した写真だけを載せる運用をおすすめします。こうすることで、「この写真は義両親に見られたらどう思うかな…」と共有範囲に悩む必要がなくなり、気持ちが楽になります。
メリット2: 写真・動画を家庭ごとに整理でき、思い出を振り返りやすい
アルバムを両家別々にすることで、実家用と思い出と義実家用の思い出を分けて整理できます。パパ側・ママ側それぞれの家族との写真が分かれていれば、後から見返す際に「これは〇〇ちゃん(子ども)とおじいちゃん(父方)と遊びに行った時のアルバムだな」と文脈がすぐに分かりやすくなります。
実家のアルバムを開けば主に実親との思い出が、義実家のアルバムを開けば義親との思い出がまとまっているため、それぞれのアルバム内でストーリー性をもって振り返ることができるのです。
一つのアルバムに全ての写真が混在している場合、祖父母が自分に関係ない相手側の親族の写真まで見ることになります。別アルバムであれば、各祖父母は自分たちに関係する写真だけを集中して楽しめるので閲覧体験が向上します。「○月○日はお宮参りで妻の両親と…」「○月△日は夫の実家に遊びに行って…」という具合に、アルバムが分かれていれば頭の中で状況を整理しやすいとの意見もあります。
メリット3: 両家間のいざこざを避け、祖父母に気兼ねなく投稿できる
アルバム分割の大きなメリットとして、両家の祖父母同士のトラブルを避けられる点も挙げられます。一つのアルバムに両方の祖父母がいる場合、投稿した写真をきっかけに予期せぬ誤解や嫉妬が生まえるケースがあります。
例えば、「実家ばかり頻繁に訪ねている」ことが写真で伝わってしまい、義両親が寂しがったり不満を持ったりするかもしれません。逆に義実家でのイベント写真が多いと、実両親が「うちにはあまり来てくれない」と感じる可能性もあります。アルバムを最初から分けておけば、それぞれのアルバムには各祖父母に関係する出来事しか共有されないため、こうした比較や勘繰りが起きにくくなるのです。
主夫ブロガーの「こっちゅう」さんも、「あえて両家別々にしない!」派の意見として、「二つグループを作ること自体が揉める原因になるかもしれない」と指摘しています。裏を返せば、両家別々にしておけば余計な気遣いや摩擦の火種を未然に排除できるということです。
このように、両家別々にすることで祖父母同士の見えない張り合いや嫁・姑間の気疲れをぐっと減らし、投稿者であるママ・パパ自身も気兼ねなく写真をアップし続けることができる環境を整えられます。
みてねを両家別々にするデメリット
一方で、みてねのアルバムを両家別々にする場合には注意すべきデメリットが3つあります。続いて、別々運用の主なデメリットを詳しく解説します。
デメリット1: 写真を両方にアップする手間が増える
両家別々のアルバムにすると、同じ写真を2回アップロードする手間が発生する点は避けられません。特に両方の祖父母に見せたい写真の場合、実家用アルバムと義実家用アルバムの両方に重複して投稿する必要があります。
育児に忙しい中でこの2度手間が地味に負担になります。実際、とあるママは「慣れるまでは(別々アップが)なかなか面倒でした。特に産後は大変なので、夫には自分のアルバムは自分でアップしてと伝えました」と語っており、最初は重複投稿に苦労したそうです。
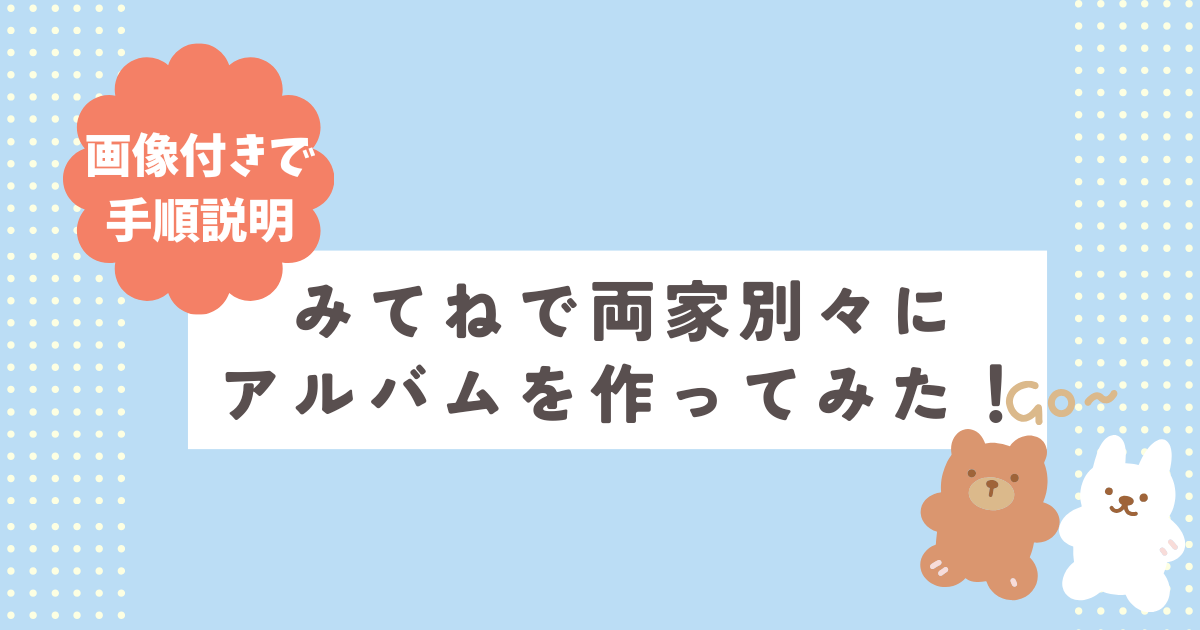
この家庭では夫婦でアルバムを分担管理することで何とか手間を分散したとのことですが、それでも1枚の写真を2回投稿する作業自体は避けられません。
デメリット2: アルバムを切り替える必要がある
みてねの無料プランでは一つのアカウントにつき管理者(親)として作れるアルバムは1つと決まっています。そのため、両家別々にアルバムを作る場合、多くの家庭ではママとパパそれぞれ別のアカウントで別アルバムを作り、お互いを招待し合うという形をとります。
この方法自体は可能なのですが、問題はアルバム間の行き来が面倒になることです。
アプリ上で複数アルバムを切り替えられるとはいえ、写真を投稿するとき毎回「これはどちらのアルバムに上げたっけ?」と気を遣ったり、コメント欄や閲覧履歴を確認するのに別々のアルバムをチェックしなければならなかったりします。
特に、ログインアカウント自体を切り替える必要がある場合、都度ログアウト→ログインの手順が発生するため、せっかくの「ワンタップで簡単共有」という手軽さが損なわれてしまいます。
デメリット3: 有料版「みてねプレミアム」の契約費用が2倍必要になる
みてね自体は無料で十分使えるアプリですが、容量無制限・3分超の動画アップ・写真ごとの公開範囲設定などが可能になる有料プラン(みてねプレミアム:月額480円)も提供されています。もし両家別々にアルバムを作った状態でプレミアム機能を使いたい場合、両方のアルバムごとに課金が必要になる点に注意が必要です。
プレミアム会員は1つのアルバムの管理者が契約すれば、そのアルバム内の家族全員が有料機能を利用可能という仕組みですが、アルバム自体が2つ存在する場合はそれぞれ別個に契約しなければなりません。つまり、ママ管理のアルバムとパパ管理のアルバムそれぞれで月額480円ずつ支払う必要があり、料金は実質2倍(約960円/月)になります。
機能面でも、2つのアルバムを跨いで写真・動画を整理したり閲覧履歴を一元管理したり、といったことは現状できません。プレミアム限定の1秒動画もアルバム単位ですので、別々アルバムだと例えば「実家アルバム版1秒動画」と「義実家アルバム版1秒動画」が別々に作成されることになります。
なお、「最初からみてねプレミアムに入って写真ごとに公開範囲を細かく設定すれば、そもそも両家別々にする大きな目的は果たされる」という指摘もあります。プレミアム版では1枚1枚の写真について「妻の両親のみ」「夫の両親のみ」といった公開先の個別指定が可能なため、1つのアルバム内で両家向け写真を出し分けることも技術的には可能です。
みてねは両家別々と一緒、どっちがよいの?
結局のところ、みてねのアルバムを両家別々にするか一緒にするかは、各家庭の状況によって答えが異なるのが実情です。それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、以下のポイントで判断するとよいでしょう。
まず、家族間の人間関係が良好で、お互いに気を遣いすぎない間柄なら「一緒」の方が手軽です。ひとつのアルバムにまとめれば投稿の手間は半減し、子どもの思い出も一元管理できます。現に、先輩パパママの中には「無理に両家別々にする必要はない」という意見も多いです。主夫ブロガーのこっちゅうさんも、「孫だけの写真を基本的にアップすればOK。祖父母は自分の孫と自分の子以外の写真には興味がないものだし、グループを2つ作る方がかえって揉める可能性がある」と述べています。

要は、アルバムを分けずに孫中心の写真だけ共有していれば十分で、祖父母同士を同席させても問題は起きにくいという考え方です。例えば祖父母本人が写っている写真については、みてねでは共有せず個別にLINE等で送るなど配慮すれば、もう一方の祖父母が嫌な思いをする心配もありません。
次に、義両親との関係にストレスがあったり、両家間で温度差が大きい場合は「別々」にする方が無難かもしれません。コメントへの感じ方や交流頻度への満足度は各家庭で違います。前述のように、「義母からのコメントが重くて投稿が憂鬱」というママも実際に存在します。
そうした場合、思い切ってアルバムを分けてしまえば、片方の祖父母だけにフェードアウトしてもらうことも可能です。別々に運用しているママからは「義実家への写真アップは夫に任せ、自分は実家向けのみ気楽にやっている」といった声もあり、負担軽減につながったケースがあります。
もちろん、アルバムを分けても義両親の過干渉がゼロになるわけではありませんが、少なくとも自分の実家向けアルバムでは心穏やかに使える分、ストレスは大きく減るでしょう。
要は、両家一緒か別々かに絶対的な正解はありません。大切なのは、「自分たち家族(夫婦と子)にとって一番心地よい使い方は何か」を基準に決めることです。周囲の家庭と比べて「うちは冷たいかな…」などと感じる必要も全くありません。
例えば、「義母には写真を見せない選択をした」という家庭もあれば、「毎日まとめてLINEで送ることにした」という家庭、「みてねの代わりに共有Googleフォトに移行した」という家庭など様々です。「家族なんだから全部見せるべき」などと義務感を抱える必要はなく、自分が不安に感じる写真は無理に公開しないという選択肢も大切です。
よくあるトラブル
最後に、実際にみてねを家族で使う中でよく起こりがちなトラブル事例とその背景を紹介します。両家一緒・別々にかかわらず参考になる点ですので、事前に知っておきましょう。
その1: 義母からの過剰なリアクション・干渉に悩まされる
「お義母さんのコメントが長文すぎて正直しんどい」「投稿のたびに何か反応されるのでプレッシャーを感じる」──これはママたちからよく聞かれる声です。
孫を思う気持ちから義母(義父の場合も)が毎回熱心にコメントしてくれるのはありがたい反面、そのテンションの高さや頻度に戸惑うケースがあります。実例として、「写真を投稿するたび義母から長文コメントが届き、育児アドバイスが次々書かれる」「『もっと投稿して』と催促される」など、善意ゆえに過熱しすぎて負担になるケースが報告されています。悪気はなくても毎回反応されると「ちゃんとしなきゃ」と身構えてしまい、気軽に投稿できなくなってしまいます。
この背景には、SNSやアプリ上での距離感に対する世代間ギャップもあります。義両親世代はSNS文化に不慣れな場合も多く、ネット上での適切な距離感が分からず善意で踏み込みすぎてしまうことがあります。
また、「嫁ともっと距離を縮めたい」「孫にたくさん関わりたい」という気持ちから、一生懸命リアクションしてしまう面もあるようです。しかし受け取る側のママにとっては、その熱意がプレッシャーや精神的負担につながってしまうことも少なくありません。
こうした場合、コメントの通知をオフにする、夫からさりげなく伝えてもらう、あるいは思い切って義母だけアルバムから外れてもらうなどの対処を検討する必要があるでしょう。
その2: コメント内容に傷つき、投稿するのが憂鬱になる
祖父母からのコメント量よりも内容そのものがストレスになってしまうケースもあります。たとえば投稿した写真に対して「『この服寒そうじゃない?』って言われて、なんだか責められてる気分…」と落ち込んでしまうママの声があります。
悪気のない一言でも、育児に奮闘する親にとっては価値観の違いを指摘されたように感じたり、「自分の育て方を否定された?」と受け取ってしまったりするのです。
文字だけのやり取りでは微妙なニュアンスが伝わりにくく、特に祖父母世代と言葉の感じ方がズレやすい傾向があります。コメントした本人は純粋に孫を心配して「薄着では?」と言ったつもりでも、ママからするとチクリと批判されたように感じてしまうこともあります。
さらに、毎回コメントが付くことで「次は何か言われるんじゃないか…」と投稿自体が憂鬱になるケースもあります。実際、「コメントが怖くて投稿するのがイヤになってきた」という声もSNS上で見られました。
その3: 投稿写真の無断使用・二次利用にヒヤリとする
家族だけのアルバムとはいえ、共有した写真が予期せぬ形で拡散されてしまうこともあります。実際にあった例として、「年賀状にうちの子の写真が勝手に使われていてびっくり…事前に一言あれば良かったのに」というケースや、「義家族が親戚に孫の写真を転送してしまった」「アルバムからスクショした写真をSNSに無防備に載せてしまった」などが報告されています。家族間とはいえ、親としては「どこまで共有されてしまったのか不安になる」というのが本音でしょう。
この背景には、祖父母世代のデジタルデータに対する認識の違いがあります。年配の方にとって写真は「みんなで見て良いもの」「家族なら自由に使って構わない」という感覚が強く、データの二次利用やプライバシー意識が若い世代ほど高くない場合があります。
とりわけ、可愛い孫の写真は「自慢したい」「周りにも見せたい」という気持ちから、つい善意で広げてしまうことがあるようです。2023年には、ある祖父母がSNSに孫の実名や写真を隠さず投稿して炎上するといった騒動も起きています。
この問題への対策として、事前にルールを決めておくことが重要です。例えば、「アルバムの写真は他の用途に使わないでね」「もし使いたい場合は一言声をかけてね」といった基本的な取り決めを最初に周知しましょう。
みてねプレミアムでは写真のダウンロードを禁止する設定も可能なので、どうしても心配な場合は検討しても良いかもしれません。いずれにせよ、「ネットに上げた写真は思わぬところに拡散し得る」というリスクを祖父母世代にも理解してもらい、家族間でも節度ある取り扱いをしてもらうことが大切です。
まとめ:負担がかからないようにルール作りしよう
みてねを両家で別々にするか一緒にするか迷ったとき、そして家族アルバムを円満に続けていくために最後に強調したいのは、「家族内のルール作り」の大切さです。どんな共有スタイルを選ぶ場合でも、事前に家族で使い方の約束事を決めておくことで、後々のトラブルや心の負担を軽減できます。
さらに、コメントや写真利用に関するマナーも共有しておきましょう。祖父母には「みんなが見られる場所なので、ネガティブなコメントは控えてほしい」「写真を他の人に転送するときは教えてね」など、事前にやんわりお願いしておくと安心です。みてねの設定機能も積極的に活用しましょう。
「コメント欄で嫌な思いをするくらいなら制限をかけてしまう」のも一つの手ですし、閲覧履歴を非表示にする設定(プレミアム機能)を使えば「ちゃんと見ているかしら…」という祖父母側の心配も和らげられます。要は、管理者であるママ・パパが無理なく安心して使い続けられる距離感とルールを見つけることが何より大切です。
みてねは本来、家族みんなで子どもの成長を楽しく見守るための素晴らしいツールです。せっかく家族の絆を深めたくて始めたのに、それが原因でモヤモヤしてしまっては本末転倒ですよね。
だからこそ、今回ご紹介したメリット・デメリットやトラブル事例を参考に、ぜひご家庭に合ったルールを作ってみてください。そうすることで、みてねがストレスではなく喜びを共有する場として機能し続け、家族アルバムが楽しい思い出作りの一助となることでしょう

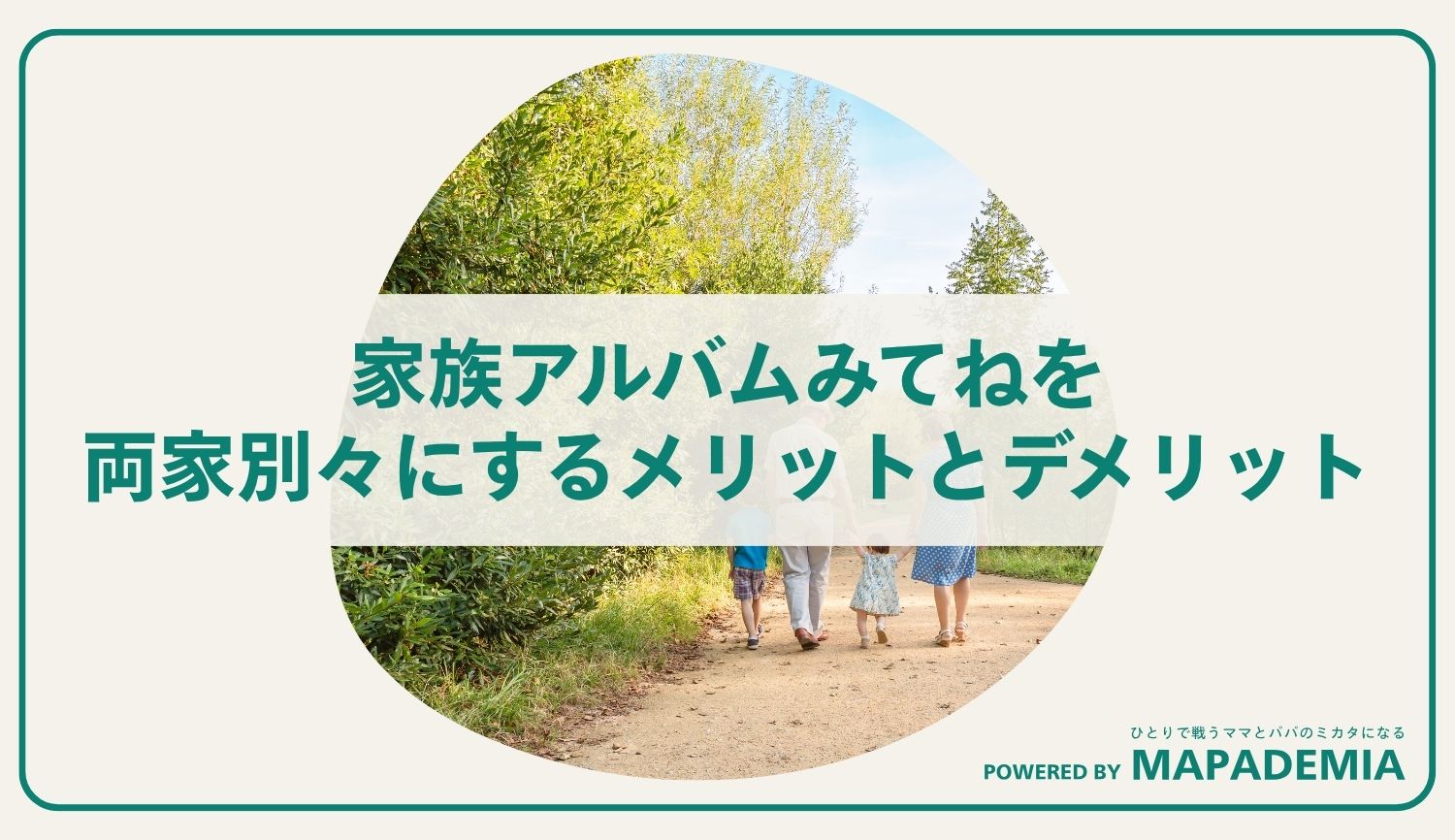









コメント