キラキラネームとは、一般的に使われない言葉や漫画・アニメのキャラクター名、難読な当て字などを用いた奇抜な名前のことです。例えば、実際に名付けられた例として「光宙(ぴかちゅう)」や「黄熊(ぷう)」などが挙げられ、初見では読めない名前が特徴です。
近年、このような「キラキラネーム」を子どもにつける親に対して、ネット上やメディアで「親がやばい」「低脳だ」といった辛辣な評価が下される場面が見られます。
本記事では、その理由を複数の観点から考察し、背景にある社会的な要因や時代による名前観の変遷についても詳しく解説します。親の愛情と社会的な受容のバランスをどのように取るべきか、専門家の意見やデータを引用しながら探っていきます。
キラキラネームをつける親がやばいと言われる理由
キラキラネームを子どもに名付ける親が「やばい」と言われてしまう主な理由として、考えられるものは大きく3つあります。ここでは、その3つの理由を順に説明します。
理由1:子どもの将来に不利益を与える可能性が高い
第一の理由は、キラキラネームが子どもの将来に不利益をもたらす可能性が高いことです。名前は本来、他人が呼び識別するためのものですが、読みづらい奇抜な名前はそれ自体が子どもにとってハンデになりえます。
実際、「2ちゃんねる」創設者の西村博之氏は「誰にも読めないような名前を子どもにつければ、いじめに遭ったり就職で不利になるなど、将来的に子どもがハンディを背負うことになる。そういったデメリットを想像できない親は頭が悪い」と指摘しています。

これは、親が目先の「特別感」や「かわいさ」ばかりを優先してしまい、子どもの将来を十分に考えていないという批判です。
現役予備校講師の林修氏も、自身の経験から「難読な名前の子どもほど成績が低い傾向があった」とテレビ番組で語っています。彼がテストの成績順に生徒の名前を並べたところ、ある点数を境に急に読めない名前が増えたといい、逆に東京大学の合格者の名前リストでは「全員の名前が読めた」といいます。このエピソードを踏まえ林氏は、「テストの点数と名前の読める読めないには、ある程度の相関性がある」と述べています。
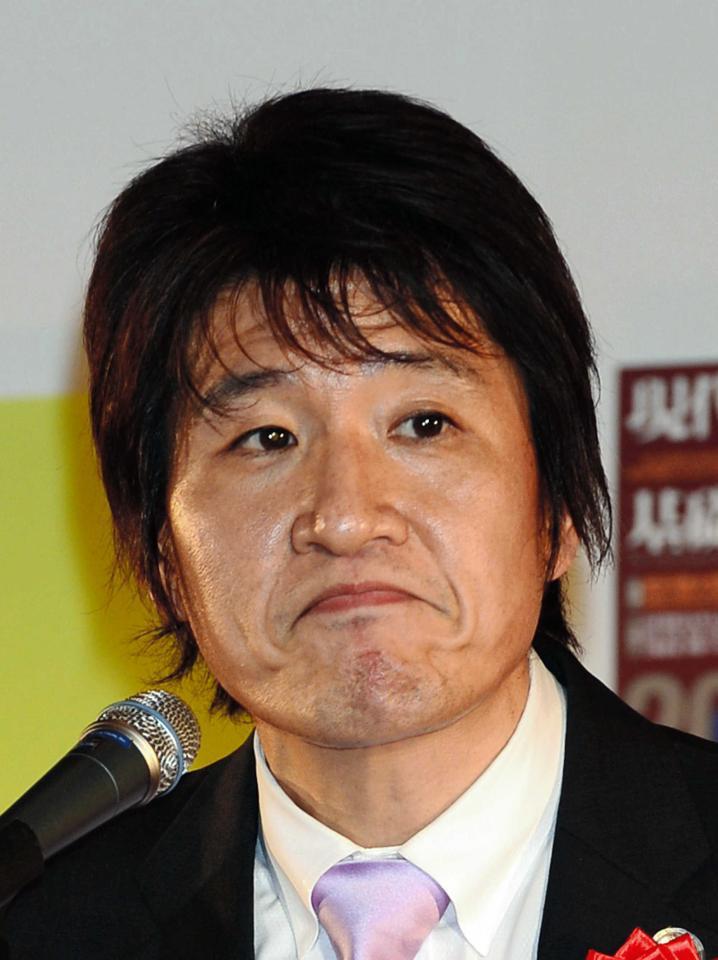
確固たる統計データに基づいた主張ではないものの、「難読名前の子は学業面でも不利益を被りやすいのではないか?」という示唆として受け止められ、多くの視聴者に衝撃を与えました。
理由2:読めない名前は周囲に迷惑をかけ、常識や社会性を疑われる
第二の理由は、難読な名前が周囲に与える迷惑や負担です。名前は本人だけのものではなく、「社会の共有物」であると命名研究家の牧野恭仁雄氏は指摘します。

たとえば、読み方が分からない名前は学校や医療の現場で支障をきたします。実際に教育現場では、難読名の児童・生徒への対応に先生方が頭を悩ませており、出席をとるたび読み間違えて訂正を求められる煩わしさを子ども自身が一生抱えるケースもあります。
牧野氏によれば、子どもが成長して学校に通えば教師が、病気になれば医療従事者が、その読めない名前のために余計な労力を費やすことになり、現に教育・医療現場では負担が増えているといいます。
社会生活においても支障があります。たとえば意識不明の状態で救急搬送された場合、名前の読み取りに手間取って処置が遅れたり、漢字の取り違えで患者認識に混乱が生じれば、命に関わる事態さえ起こりえます。また、公式の場で氏名を読み上げられる際に読めない名前は高確率で誤読され、あまりに奇抜だと周囲から失笑を買うことすらあります。
このように、読めない名前は必ず誰かの迷惑になるものですが、実際には「他人に読めなくても気にしない」「こう読ませればいいでしょ」と開き直る親も少なくないのが実情です。もっとも、牧野氏は「だからといって名付け親の知能が低いとか性格が歪んでいるというわけではない」とも述べています。
むしろ問題の根本は、そうした親たちが自分の身近な知人範囲しか想像できず、見ず知らずの他人が大勢いる広い社会というものをイメージできていないことにあるのだと指摘しています。いずれにせよ、社会常識より自分のこだわりを優先した名前は周囲に負担を強いるため、「配慮が足りない」「非常識だ」と批判され、「親がやばい」と見做される理由となっています。
理由3:名付けが親の自己満足や自己顕示に偏っている
第三の理由は、子どもの名前が親の自己満足や自己顕示欲の表れになってしまっていることです。親にとって子どもの命名は一世一代の大仕事であり、本来は子どもの幸せや将来を願って行うものです。
しかし、キラキラネームの場合、しばしば「他人とは被らない特別な名前にしたい」「とにかく響きが可愛いから」「目立ってカッコいい名前を付けたい」といった親側の思い入れや自己満足が優先されがちだと指摘されています。
事実、西村博之氏は「親自身の『特別感を出したい』『雰囲気が可愛い』といった理由で変わった名前を付けてしまうと、子どもの将来を台無しにする恐れがある。親になる人たちはもっとよく考えてほしい」と苦言を呈しています。特別で個性的な名前を贈りたいという親心が暴走し、「名前」を目的化してしまって本末転倒になっているというわけです。
「個性」を尊重するあまりに周囲の目を過剰に意識しているケースもあります。牧野恭仁雄氏によれば、キラキラネームを付ける親たちは「個性」「自由」を唱えつつ、「平凡な名前だと思われたくない」「人と被らない名前にしたい」という思いが強く、「本や雑誌で見た名前」「TVで話題になった名前」「みんながやっている」といった情報に踊らされがちだと言います。
つまり、本当の意味で独創的に考えたわけではなく、他人に流されながら「人とは違う特別感」を求めているに過ぎないのです。こうした傾向は牧野氏が「過剰適応」と表現するもので、他人から浮くことを恐れて器用に流行に乗ってきた人々が、子どもの名前を使って「人との違い」を示そうとしている側面もあると指摘されています。
結果として、子どもの名前が親の自己顕示欲発散の手段になってしまっているとすれば、世間から「親のエゴのせいで子どもが振り回されている」と見られてしまい、「やばい親だ」と思われるのも無理はありません。
キラキラネームをつけたがるのはなぜなのか?
以上のような批判がある一方で、なぜそもそも親たちはキラキラネームをつけたがるのでしょうか。その背景には、現代ならではの様々な要因が指摘されています。主なものを挙げると次のとおりです。
※ 解説列をワイドに取り、文章が読みやすいように調整しています。
| テーマ | 要旨 | 解説 | 参考 |
|---|---|---|---|
| 唯一無二の名前で特別扱いしたい親心 | 少子化と乳児死亡率の低下で「オンリーワン」を求める親が増加。 | 兄弟姉妹が少なく、一人あたりに手間をかけられる時代背景から、平凡な名では物足りないと感じる親もいる。 | fujipon.hatenablog.com |
| 「個性重視」志向と差別化ニーズ | 「他の子と違う名で輝いてほしい」願望から、意図的に一般的な名を外す。 | 命名相談の現場でも「平凡と思われたくない」「珍しい名にしたい」という声が根強く、個性化のための名付けが選ばれる。 | canij.com / president.jp |
| メディアや流行の影響 | 雑誌やTVが個性的な名を紹介し、模倣がブーム化。 | 平成以降、「皇帝(しいざあ)」「今鹿(なうしか)」「一二三(わるつ)」などの極端な名が話題化し、実際の命名例も登場。 | canij.com / president.jp |
| 従来の命名観からの解放感 | 平和で豊かな時代の世代は命名規範に縛られにくい。 | 伝統的な「〇〇子」「〇〇郎」から離れ、英語風や新しい当て字も受け入れやすくなっている。 | president.jp |
| 良い字画や意味を詰め込みたい欲求 | 縁起や美しい意味の漢字を詰め込みすぎて難読化。 | 例:「心」と「愛」を組み合わせた「心愛(ここあ)」など、善意の詰め込みが結果的に読みにくい名につながる。 | fujipon.hatenablog.com |
これらの要因から分かるように、キラキラネームを付ける親の多くは決して悪意や軽率さだけで名付けているわけではなく、むしろ強い愛情ゆえに「少しでも良い名前にしたい」「この子だけの特別な名前を贈りたい」と願っての行動である場合も多いのです。
ただ、その善意が空回りしてしまい、結果として子どもや周囲に負担を強いる名前になってしまうことに問題があります。次章では、そうした親たちが「低脳」と酷評されてしまう背景について、社会的な視点から掘り下げます。
キラキラネームをつける親が低脳と酷評される背景
一部で「キラキラネームをつける親=低脳(頭が悪い)」とまで言われてしまう背景には、いくつかの社会的・文化的な文脈があります。その代表的なものを挙げてみましょう。
※ 解説列を最大限広く取り、折り返しを減らして読みやすくしています。
| テーマ | 要旨 | 解説 | 参考 |
|---|---|---|---|
| ネットスラング「DQNネーム」の浸透 | 掲示板発祥の蔑称「DQNネーム」が原型。 | 「DQN」は非常識で教養がない人を指す俗語で、難読奇妙な名を付ける親=低俗層という偏見が広がった。この風潮が後のキラキラネーム批判の土台になった。 | — |
| 西村博之氏の発言による影響 | 2017年以降の発言が賛否を呼ぶ。 | YouTubeやSNS、プレジデント誌で「頭の悪い親ほど付けたがる」「東大合格者にキラキラネームはいない」などの持論を展開。賛同と反発を呼び、「親がバカ」という図式の定着に影響を与えた。 | canij.com / times.abema.tv |
| 教育現場からの証言と示唆 | 教師が名と成績の傾向を指摘。 | 林修氏ら教育関係者が「読めない名の子は成績が低い」「そういう親ほど学校にクレームが多い」と証言。名付けに価値観や教育姿勢の差が現れる可能性を示唆。 | fujipon.hatenablog.com |
| 学術研究や統計による相関 | 米研究で名と親の教育・収入の関連。 | 『ヤバい経済学』では出生データから、教育水準の低い家庭ほど特異な名を付ける傾向を報告。日本でも同様の見方が広まり、「知的・経済的レベルの低さの表れ」という印象が定着した。 | j-cast.com / daily.co.jp |
以上のように、ネットスラングから著名人の発言、教育現場の声やデータまで、多方面からキラキラネームの親に対するネガティブな情報が蓄積された結果、「キラキラネームを付ける親は低脳だ」「非常識で子どもの将来を考えていない」といった評価が生まれています。
しかし一方で、専門家からは「名前の奇抜さと親の知能は本質的には関係がない」との指摘もあります。命名研究家の牧野氏は「キラキラネームは個性とも知能とも関係ない」と断言しており、京都大学の小林康正教授も「問題なのは一部の度を越した珍妙な名前であって、すべてのキラキラネームが悪いわけではない」と述べています。要は、「キラキラネーム=低脳」という図式は極端であり、そこには親側の社会経験や価値観の問題、あるいは周囲の偏見といった複合的な要因が絡んでいると言えるでしょう。
名前のあり方は時代によって変化する
キラキラネームの議論を考える上で忘れてはならないのは、「何が奇抜で何が普通か」という名前の感覚は時代とともに変化するという点です。実は、他人が読めないような変わった名前は平成以降に始まった新しい現象というわけではありません。
例えば昭和初期の日本にも、現在の感覚から見ればキラキラネーム顔負けの珍名が存在しました。命名研究家の牧野氏が紹介する例では、「丸楠(まるくす)」「亜歴山(あれきさんどる)」「武良温(ぶらうん)」「六十里二(むっそりーに)」といった名前が昭和初期に実際につけられており、一見すると平成のキラキラネームかと思いきや、れっきとした戦前の命名だったのです。
文豪・森鷗外や与謝野晶子が我が子に付けた名前も、当時としてはかなり風変わりなもので、奇抜な命名そのものは古くから散見されました。ただしそれが大勢の人に模倣されて流行になることはなく、あくまで一部の変わり者の例だったのです。

その後、戦後しばらくの日本では奇抜な名前は下火になります。1950〜80年代に子育て期を迎えた親たちは戦中戦後の貧困や混乱を生き抜いた世代であり、堅実で安定志向の価値観を持っていました。そのため子どもの名前も比較的オーソドックスで実直なものが好まれ、「太郎」「花子」「◯◯子」といった伝統的で読みやすい名前が多かったのです。
状況が変わり始めるのは平成に入ってからです。1990年代以降、日本社会が豊かで安定し個性や多様性を尊重する風潮が強まると、再び奇抜な名前が増加し始めました。テレビや雑誌で珍しい名前が「キラキラネーム」として面白おかしく紹介されると、それをきっかけに「うちの子もユニークな名前にしよう」と考える親が増え、キラキラネームは一つのムーブメントになったのです。名付けのあり方にも流行が生じ、平成後期にはネット上で「キラキラネーム一覧」が話題になったり、毎年のように奇抜な名前ランキングがニュースになったりしました。
しかしさらに時代は進み、令和の現在では極端なキラキラネームは次第に下火になりつつあるとも言われます。一時期は「悪魔」「光宙(ピカチュウ)」のようなギャグに近い名前が注目を集めましたが、あまりに奇抜な名前を見ても人々が驚かなくなり、かえって陳腐だと受け取られるようになってきたのです。
令和の親世代の価値観としても、ピーク時の反動からか「あそこまで極端なのはちょっと…」という空気が出始めています。実際、最近の名づけランキング上位を見ると、一見読めない当て字風の名前もありますが、読み方自体はある程度想像できる「程よい個性」の名前が増えてきています。極端なケースほどニュースになりにくいだけかもしれませんが、少なくとも社会全体としては命名の過度な暴走にブレーキがかかりつつあるようです。
まとめ:愛情の有無と他者の受け入れ具合のバランス
キラキラネームをめぐる問題は、突き詰めれば、「親の愛情」と「社会的受容性」とのバランスの問題と言えます。ユニークな名前を付けたいという親心の根底には、子どもへの深い愛情や期待があります。実際、キラキラネームを付ける親自身も「我が子のためを思って」名付けている場合がほとんどでしょう。
しかし、どんなに思い入れが強くても、名前は子ども自身が生涯背負っていくものであり、周囲の人々にも常に使われる社会的なラベルです。親のエゴや自己満足だけで突き進めば、子どもが将来背負うかもしれない不利益や周囲への迷惑を見落としてしまいます。
重要なのは、親の愛情を適切な形で表現しつつ、他者から受け入れられやすい範囲で個性を追求することです。奇をてらった名前で愛情を示すのではなく、子どもの人生に寄り添い、社会の一員として生きやすい名前を選ぶこともまた愛情の表れでしょう。
時代によって名前の価値観は変わるとはいえ、子どもの幸せと社会での生きやすさを最優先に考えるという命名の基本は不変です。奇抜さと実用性、親の想いと社会の常識、その両者をうまく両立させたところに、本当の意味で良い名前があるのではないでしょうか。










コメント